鉄の方が有利な用途とは?ステンレスに勝る場面を解説
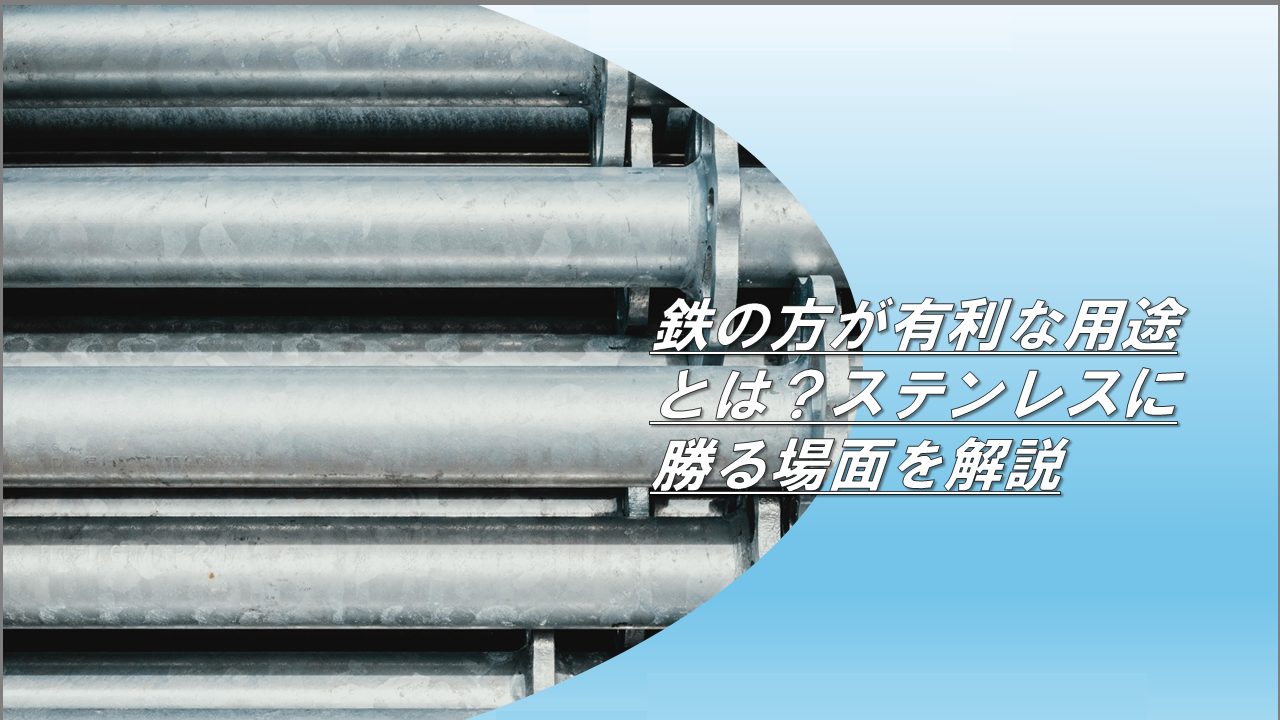
金属加工.comをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、山梨県・長野県にて切削加工やろう付けを行っている 北東技研工業株式会社 が運営しております。
金属加工に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
鉄とステンレスは、どちらも金属加工の現場で非常に多く使われる素材ですが、その特徴は大きく異なります。まず、鉄とは主に炭素鋼(炭素含有量が0.02〜2.0%の鉄)を指し、炭素量や添加元素の違いによって強度や加工性が変化します。一方で、ステンレスは鉄をベースにクロム(Cr)を10.5%以上含有した合金鋼で、錆びにくく、耐食性に優れるのが最大の特徴です。
しかし「耐食性が高い=常に優れている」というわけではありません。実際には、コスト・加工性・強度・熱伝導性など、複数の観点から見ると、鉄の方が有利な場面も多く存在します。ここでは、ステンレスよりも鉄が優位に立つ具体的な用途や理由を解説していきます。
コスト面で圧倒的に有利な鉄
鉄は材料費が安価
鉄が最も評価される理由の一つは、やはり「価格」です。ステンレスはクロムやニッケルなどの高価な合金元素を含むため、同じ形状・重量の部品でも単価は鉄の2〜4倍になることがあります。大量生産される構造物や部品では、この差が非常に大きく影響します。
例えば、自動車のシャーシ、建築鉄骨、橋梁部材などは大部分が炭素鋼で作られています。これらの部品は大量に使用されるうえに、メンテナンスや塗装による防錆対策が可能であるため、あえて高価なステンレスを使う必要がありません。
防錆処理で十分対応できる場面も多い
近年では、防錆塗装や溶融亜鉛メッキ(いわゆる「ドブ付けメッキ」)などの技術が発達しており、鉄でも長期間の耐久性を確保することが可能になっています。たとえば屋外階段や手すりなどでは、塗装やメッキを適切に行うことで、ステンレスに近い耐久性を実現できます。
つまり、「錆びやすい」という鉄の弱点は、現代の表面処理技術によって十分に克服可能なのです。
機械的強度で鉄が有利なケース
炭素量によって強度を自在に調整できる
鉄は炭素含有量を調整することで、硬さ・靱性・延性などの性質を自在に変えられます。たとえば、炭素鋼(S45Cなど)は熱処理を施すことで非常に高い強度を得られます。一方、ステンレス鋼は硬く加工しにくく、熱処理による強度向上も限られています。
高荷重を支える構造材に最適
クレーン部材、建設機械、鉄道レール、橋梁など、高い強度や剛性が求められる構造物では、鉄の方が明らかに優れています。ステンレスは延性が高く、ある程度の塑性変形を許容しますが、強度という観点では一般の炭素鋼や合金鋼に劣ります。
衝撃や摩耗にも強い鉄
鉄は、ステンレスに比べて衝撃値(靱性)が高い鋼種を選びやすいのも利点です。さらに、耐摩耗性を高めるために浸炭処理や焼入れを行うことも可能です。これにより、歯車・軸受・シャフト・カムなど、摩耗や衝撃を受けやすい部品にも多く使用されています。
加工性で鉄が勝る理由
切削・溶接・曲げが容易
鉄はステンレスよりも加工性が良く、切削抵抗が低いため工具の摩耗も少なく済みます。特にステンレスは熱伝導率が低く、切削時に熱が刃先に集中して工具が摩耗しやすい傾向があります。鉄であれば、比較的容易に穴あけ・ねじ切り・溶接・曲げ加工などを行うことが可能です。
また、鉄の溶接はステンレスに比べて溶融特性が安定しており、溶接欠陥(ピット・ブローホール・割れ)も起きにくいという特徴があります。これにより、加工コストの削減や生産効率の向上が期待できます。
精密部品や大型構造物の加工にも適する
たとえば、機械のベースフレームや産業用ロボットのアームなど、精密さと剛性を両立させたい部品には鉄が選ばれることが多いです。ステンレスは熱膨張率が高いため、加工中の寸法変化が起きやすく、高精度加工にはやや不向きです。
熱伝導性・磁性などの物理特性で鉄が優れる場面
熱伝導性の高さを活かす用途
鉄はステンレスよりも熱伝導率が高く、熱を効率的に伝えることができます。このため、鍋・フライパン・ヒーター部品・ボイラー管など、熱を素早く伝える必要がある製品では鉄が適しています。ステンレス製の調理器具でも、底面に鉄やアルミを貼り合わせて熱伝導を改善しているものが多いのはそのためです。
磁性を必要とする部品
鉄は磁性を持つため、モーターコア・トランス鉄心・電磁石など、磁気を利用する製品では欠かせない素材です。一方、ステンレスはオーステナイト系の場合、非磁性であり、磁力を必要とする用途には適しません。磁性制御を目的とする精密機器や電気機器の分野では、鉄の存在は非常に重要です。
耐熱性・熱処理性での優位性
高温下での強度保持
ステンレスは耐酸化性に優れていますが、高温環境下での機械的強度は鉄鋼の中でも合金鋼の方が高い場合があります。特にクロムモリブデン鋼(SCM材)は、ボイラー・タービン・エンジン部品などの高温・高圧環境に耐える材料として広く利用されています。
熱処理による性能向上が可能
鉄系材料は焼入れ・焼戻し・焼鈍などの熱処理で、目的に応じた硬さや靱性を得られます。ステンレスにも一部熱処理可能な鋼種(マルテンサイト系など)はありますが、熱処理効果の幅は炭素鋼や合金鋼ほど広くありません。そのため、強度や耐摩耗性を重視する部品では鉄が依然として主役です。
ステンレスより鉄が選ばれる代表的な用途
以下に、現場で鉄の方が有利と判断される主な用途を挙げます。
- 建築構造物(鉄骨、梁、柱など)
- 橋梁・鉄塔・クレーンなどの大型構造物
- 機械フレーム、プレス機、工作機械ベース
- 自動車部品(シャーシ、フレーム、ギヤ)
- 電磁機器(モーター、トランス)
- 鍋、フライパン、熱交換器などの熱伝導部材
- 油圧・空圧機器のシャフト・ピストン部品
これらは、コスト・強度・加工性・熱伝導性・磁性といった複数の要素を総合的に考慮した結果として鉄が選ばれています。
鉄を選ぶ際の注意点
鉄は優れた素材である一方、錆や腐食のリスクを常に抱えています。屋外や湿潤環境で使用する場合は、以下の対策を講じることが重要です。
- 防錆塗装やメッキ処理を施す
- 定期的なメンテナンス(塗り替え、清掃)を行う
- 水分や薬品に触れる環境では、部分的にステンレスや樹脂を併用する
このような工夫を行うことで、鉄のコストパフォーマンスを最大限に活かすことができます。
まとめ:最適な素材選定が品質とコストを左右する
鉄とステンレスはどちらも優れた材料ですが、「どちらが上位」という単純な比較では語れません。耐食性が最優先ならステンレスが適していますが、コスト・強度・加工性を重視する場面では、鉄の方が明らかに有利です。
特に、構造材・機械部品・電磁機器・熱交換器など、「錆びにくさ」よりも「性能」や「経済性」が重視される分野では、今後も鉄が主役であり続けるでしょう。
最終的には、使用環境・コスト制約・製品寿命などを総合的に判断し、「最適な素材を選定する」ことが、品質向上とコスト削減の両立につながります。
いかがでしたでしょうか?
金属加工.comでは、他にも金属加工関連の情報を発信しております。他にも気になる記事がありましたら、是非ご覧ください。
金属加工.comのトップページはこちら↓

関連記事はこちら↓







