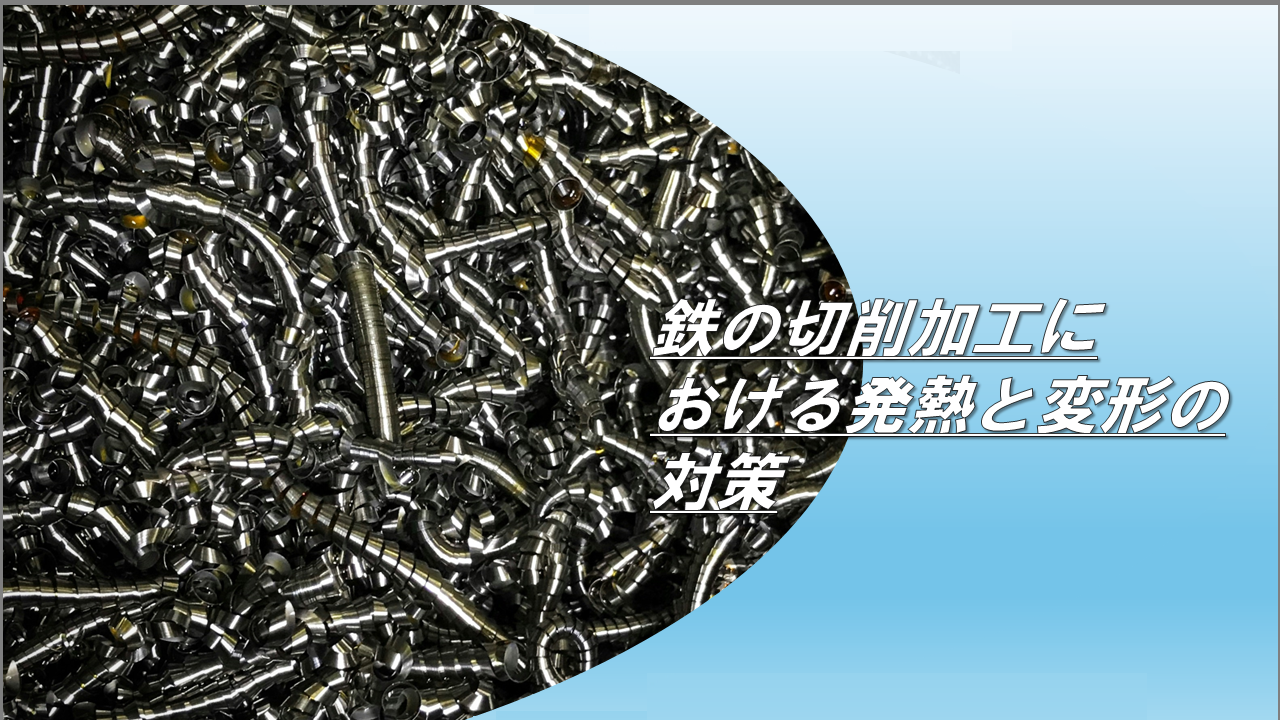鉄鋼材料のドリル加工の基本

金属加工.comをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、山梨県・長野県にて切削加工やろう付けを行っている 北東技研工業株式会社 が運営しております。
金属加工に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
鉄鋼の種類と加工性の違い
鉄鋼材料は大きく分けて「炭素鋼」「合金鋼」「ステンレス鋼」などがあります。
炭素鋼は比較的加工しやすいものの、炭素量が増えると硬度が高まり、切削抵抗も増加します。合金鋼は添加元素によって耐摩耗性や強度が高くなりますが、その分ドリル摩耗が早く進みます。
ステンレス鋼は熱伝導率が低く、切削中に熱がこもりやすいため、ドリルが焼けたり、刃先が摩耗しやすい特徴があります。
ドリル加工の基本原理
ドリル加工は、回転する刃先が材料を削り取りながら穴を形成する切削加工です。加工効率や穴精度を確保するには、切削速度、送り量、ドリル材質、クーラント供給などの条件を適切に設定する必要があります。
ドリル加工で発生しやすいトラブルと原因
ドリルの折損
最も多いトラブルのひとつが、ドリルが途中で折れてしまう「折損」です。
原因としては以下のようなものが挙げられます。
- 切削抵抗が大きすぎる
- 刃先の摩耗が進んでいる
- 切りくずが排出されず詰まっている
- 加工穴が深く、クーラントが届いていない
- 材料の硬度が高すぎる、または焼き入れ部に当たった
折損を防ぐには、切削速度を下げる・送り量を適正化する・ステップ加工を行うなどの工夫が有効です。
穴の精度不良
ドリル加工では、穴の径が設計より大きくなったり、小さくなったり、真円度や位置精度が乱れることがあります。
主な原因は以下の通りです。
- ドリルが偏芯して取り付けられている
- 刃先の左右バランスが崩れている
- 加工中にドリルがたわんでいる
- 下穴やセンターポンチがずれている
- 被削材の硬さが部分的に異なる
対策としては、ドリルの芯出しを正確に行い、必要に応じてセンタードリルで位置決めを行うことが重要です。深穴の場合はリーマやボーリングによる仕上げ加工も効果的です。
バリの発生
穴あけ加工では、貫通部に「バリ(材料のめくれ)」が発生することがよくあります。
特に軟鋼やステンレス鋼では、延性が高いためにバリが大きくなりやすい傾向があります。
バリの主な原因は以下の通りです。
- ドリルの切れ味が悪い
- 送り量が大きすぎる
- 貫通時の押し抜き力が大きい
- 裏側に支持材がない
対策としては、刃先を鋭利に保つこと、貫通直前で送りを弱めること、または裏側にバックプレートを当てて材料を支えることが効果的です。
ドリル摩耗・焼け
鉄鋼材料の加工では、熱の発生が避けられません。特にステンレスや高炭素鋼では、熱が逃げにくいために刃先が高温になりやすく、摩耗や焼けが進行します。
摩耗・焼けの原因は以下の通りです。
- 切削速度が高すぎる
- クーラントが不足している
- ドリルの材質が被削材に合っていない
- 逃げ角が不適切で摩擦が大きい
対策としては、コーティングドリル(TiAlNやTiCNなど)を使用し、適切なクーラント供給を行うことが有効です。また、加工条件を見直して切削温度を抑えることが大切です。
トラブル別の具体的な解決策
折損トラブルの改善策
- ステップドリル加工:深穴では一気に貫通せず、一定の深さごとにドリルを抜いて切りくずを排出します。
- ドリルの剛性を高める:短いドリルを使う、またはチャックをしっかり締めて振れを抑えます。
- 切削条件の見直し:送りを小さくし、回転数を下げることで負荷を軽減します。
- クーラント供給の強化:エアブローや内部給油タイプのドリルを使用し、切りくず排出と冷却を両立します。
穴精度不良の改善策
- センタードリルによる位置決め:最初にセンタードリルで浅い穴を開け、ドリルのブレを防ぎます。
- 高精度チャックを使用:スリーブやコレットチャックを使い、ドリルの偏芯を抑えます。
- ドリルの再研磨:刃先角度やリップクリアランスを確認し、左右バランスを整えます。
- 仕上げリーマの使用:穴径精度が求められる場合は、リーマ加工で仕上げるのが理想です。
バリ発生の改善策
- 裏側の支持:裏面に木板などのバックアップ材を置き、貫通時の変形を抑えます。
- 送り速度の調整:貫通寸前で送りを弱め、押し抜き力を軽減します。
- バリ取りカッターの併用:後工程で専用工具を使用してバリを除去します。
- ドリル形状の最適化:先端角の大きいドリル(135°など)を使用すると、貫通時のバリが減少します。
摩耗・焼け対策
- 適正な切削速度の設定:鉄鋼の場合、一般的に15〜25 m/min程度が目安です(材質によって変動)。
- コーティングドリルの使用:TiAlN、TiCN、DLCなどのコーティングにより耐熱性が向上します。
- 切削油の最適化:水溶性クーラントを使用して十分に冷却し、ドライ加工を避けます。
- 休止加工:連続加工を避け、一定の間隔で工具を冷却します。
鉄鋼ドリル加工での材料別ポイント
炭素鋼(S45Cなど)
比較的加工しやすいが、炭素量が増えると硬くなるため、摩耗が早くなります。
切削速度は中程度に設定し、HSSコバルト系ドリルが適しています。
合金鋼(SCMなど)
硬度が高いため、超硬ドリルやコーティングドリルが望ましいです。
特にSCM材では焼き付きが起こりやすいため、冷却重視で加工を行います。
ステンレス鋼(SUS304など)
熱がこもりやすく、加工硬化を起こすため、低速・高送りが基本です。
刃先を常に鋭く保ち、切りくずが流れるように加工するのがポイントです。
ドリル選定とメンテナンスの重要性
ドリルは消耗品ですが、適切な管理を行えば寿命を延ばすことができます。
使用後は切りくずを除去し、刃先の摩耗や欠けを点検します。摩耗が確認されたら再研磨を行い、リップ角や先端角を正確に再現することで、再利用が可能です。
また、被削材に合わせた材質選定(HSS、超硬、コーティングなど)を行うことで、トラブルを大幅に減らすことができます。
まとめ
鉄鋼材料のドリル加工は、一見シンプルに見えても多くの要因が絡み合う高度な技術です。
折損・摩耗・穴精度不良・バリなどのトラブルは、加工条件の見直しと工具選定で防止可能です。
加工現場では、「切削温度を抑える」「切りくずをスムーズに排出する」「ドリルを常に鋭利に保つ」という3つの基本を意識することが最も重要です。
正しい知識と条件設定を行えば、鉄鋼でも高精度で安定したドリル加工が実現できます。
いかがでしたでしょうか?
金属加工.comでは、他にも金属加工関連の情報を発信しております。他にも気になる記事がありましたら、是非ご覧ください。
金属加工.comのトップページはこちら↓

関連記事はこちら↓