鉄の切削加工における発熱と変形の対策
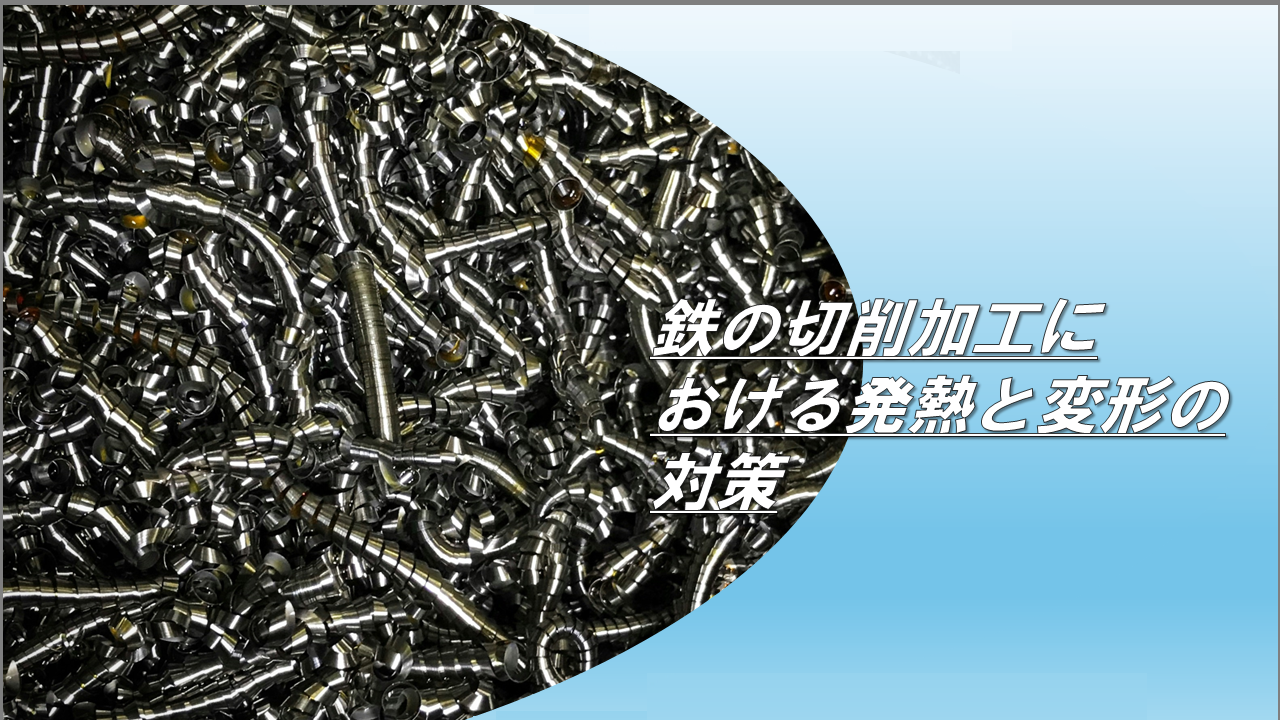
金属加工.comをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、山梨県・長野県にて切削加工やろう付けを行っている 北東技研工業株式会社 が運営しております。
金属加工に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
鉄の切削加工では、「発熱」と「変形」という二つの問題が常に付きまといます。切削点では高い摩擦と塑性変形が発生するため、加工温度が上昇し、工具の摩耗や寸法精度の低下、さらには製品の品質低下を招くことがあります。この記事では、鉄を切削する際に起こる発熱と変形のメカニズムを解説し、その原因と効果的な対策について詳しく紹介します。
鉄の切削加工で発生する熱のメカニズム
切削点の高温化の原因
切削加工では、工具の刃先と被削材の間に強い摩擦が生じます。この摩擦と被削材の塑性変形が主な発熱源です。特に鉄は粘り強く、せん断変形抵抗が高いため、切削抵抗が大きくなり、それに伴って発熱量も増加します。
また、切削中に生成される切りくずが工具に密着すると、摩擦熱が逃げにくくなり、刃先温度が数百度に達することもあります。このような高温状態が長く続くと、工具の寿命が著しく短くなるだけでなく、鉄材の組織変化や残留応力の発生につながります。
発熱の主な発生部位
切削における熱は、主に以下の三つの部位で発生します。
- せん断変形域:被削材が切りくずとして分離される直前に塑性変形する部分。ここで全発熱量の約60%が生じます。
- すくい面接触部:切りくずが工具すくい面を滑る際の摩擦熱。約30%がこの部分で発生します。
- 逃げ面接触部:工具逃げ面と加工表面の間の摩擦による熱。残り10%程度です。
発熱がもたらす悪影響
工具摩耗の加速
刃先温度が上昇すると、鉄との反応によって工具材の硬度が低下します。特にハイス工具では焼き戻し温度を超えると急激に硬度が落ち、摩耗が進行します。また、超硬工具でも高温下では酸化や拡散摩耗が進み、工具寿命が短くなります。
寸法精度の低下
発熱による被削材の熱膨張も問題です。加工中に膨張した状態で切削が進むと、冷却後に収縮し、設計寸法よりも小さく仕上がることがあります。精密部品の加工では、このわずかな膨張収縮が致命的な寸法誤差を引き起こします。
表面粗さの悪化
切削温度が高いと切りくずの流れが不安定になり、ビビり振動や摩擦痕が発生しやすくなります。結果として加工面の粗さが悪化し、製品の外観や機能面に悪影響を与えます。
発熱を抑えるための基本対策
切削速度・送り量・切り込みの最適化
切削条件は発熱量に大きく影響します。特に切削速度が上がると摩擦エネルギーが急増し、温度が上昇します。
鉄の切削では、工具寿命を優先する場合、以下のような調整が効果的です。
- 切削速度:やや低速側に設定(超硬工具で80~150m/min程度)
- 送り量:小さすぎると摩擦増、適度な値(0.05~0.2mm/rev程度)
- 切り込み:浅すぎると摩擦支配、適度な深さを確保(0.5~2mm程度)
これらをバランスよく設定することで、切削温度を下げつつ生産性を維持できます。
冷却・潤滑の活用
クーラント(切削油や水溶性切削液)の使用は、発熱対策の基本です。
冷却効果だけでなく、摩擦を減らす潤滑効果も得られます。代表的な方法として以下が挙げられます。
- フラッディング(大量供給)方式:切削点全体に大量のクーラントをかけ、熱を効率的に除去
- MQL(最小量潤滑)方式:環境負荷を低減しつつ潤滑重視の加工に適用
- エアブロー方式:乾式加工で切りくず排出と冷却を両立
鉄加工では水溶性クーラントを用いることが多く、適切な濃度管理やノズル位置の調整が温度抑制に直結します。
変形が生じる原因とそのメカニズム
熱変形
切削中の発熱が材料内部に伝わると、被削材全体が膨張します。この熱変形は、特に薄肉部品や長尺ワークで顕著です。加工中の温度分布が不均一な場合、反りや曲がりが発生し、寸法精度が乱れます。
残留応力による変形
切削加工では、材料表面に塑性変形が生じるため、内部応力が不均一に分布します。加工終了後、これらの応力が解放されると、ワークがわずかに曲がったりねじれたりします。精密部品ではこの微小な変形も許容できない場合が多く、加工後の歪み取りが必要になります。
機械的変形
切削抵抗が大きい場合、ワークの固定力や剛性が不足すると、加工中にたわみや振動が発生します。特に鉄の重切削では、工具押し込み力が強く、固定が不十分なときに形状誤差を生じやすくなります。
変形を防ぐための実践的対策
ワークの固定と支持を強化する
変形防止の第一歩は、ワークの剛性確保です。治具設計においては、以下の点を意識します。
- クランプ位置を加工点に近づける
- 支持点を多く設け、均等に荷重を分散
- 過大な締め付けによる応力集中を避ける
また、磁気チャックや真空チャックを用いる場合は、吸着力が加工抵抗に耐えられるかを事前に確認することが重要です。
加工順序の最適化
部品の形状によっては、加工の進め方で変形量を大幅に抑えることが可能です。
たとえば、全体を荒加工した後に一度応力除去焼鈍を行い、その後に仕上げ加工を行うことで、残留応力を低減できます。
また、薄肉部品の場合は、内側から外側へ、あるいは交互に削ることで熱や応力の偏りを防ぎます。
切削条件の見直し
過度な切削抵抗が変形を助長するため、送り量や切り込みを抑えた仕上げ条件を設定します。
また、切削速度をやや低く設定すると、熱の発生量を抑え、熱変形も軽減されます。
加工後の応力除去処理
高精度が要求される鉄部品では、加工後に応力除去焼鈍(ストレスリリーフ)を行うことが一般的です。
この処理により、内部に残留していた応力を緩和し、長期的な寸法安定性を確保できます。
工具材質とコーティングによる改善
工具材質の選定
鉄を切削する際は、工具材の耐熱性と耐摩耗性が重要です。
代表的な選択肢として以下が挙げられます。
- 超硬合金工具:高温でも硬度を維持しやすく、一般的な鉄加工に最適
- サーメット工具:低摩擦で仕上げ面が美しく、発熱が少ない
- セラミック工具:高温下での耐摩耗性が高いが、衝撃に弱い
- CBN工具:焼入れ鋼や高硬度材に対応、熱変形を最小化可能
加工内容に応じてこれらを使い分けることで、温度上昇を抑え、寸法安定性を向上させられます。
コーティング技術の活用
近年では、TiAlNやCrN、AlCrNなどの耐熱性コーティングが主流です。これらのコーティングは、摩擦を減らし、工具と被削材の間の熱伝達を遮断する効果があります。
結果として、刃先温度を下げ、熱変形の抑制と工具寿命延長の両方を実現できます。
まとめ:発熱と変形を抑え、安定した鉄加工を実現するために
鉄の切削加工では、発熱と変形は避けて通れない課題です。しかし、原因を理解し、切削条件・冷却方法・工具選定・加工順序を適切に最適化すれば、これらの問題を大幅に軽減することができます。
特に以下のポイントを押さえることが重要です。
- 切削条件の最適化で発熱を制御する
- 冷却と潤滑を適切に行う
- ワーク固定と加工順序を工夫して変形を防ぐ
- 応力除去や工具コーティングを積極的に活用する
これらの対策を組み合わせることで、精度の高い鉄加工と工具寿命の延長を両立でき、安定した品質の製品づくりが可能になります。
いかがでしたでしょうか?
金属加工.comでは、他にも金属加工関連の情報を発信しております。他にも気になる記事がありましたら、是非ご覧ください。
金属加工.comのトップページはこちら↓

関連記事はこちら↓






