金属材料の疲労破壊とは?
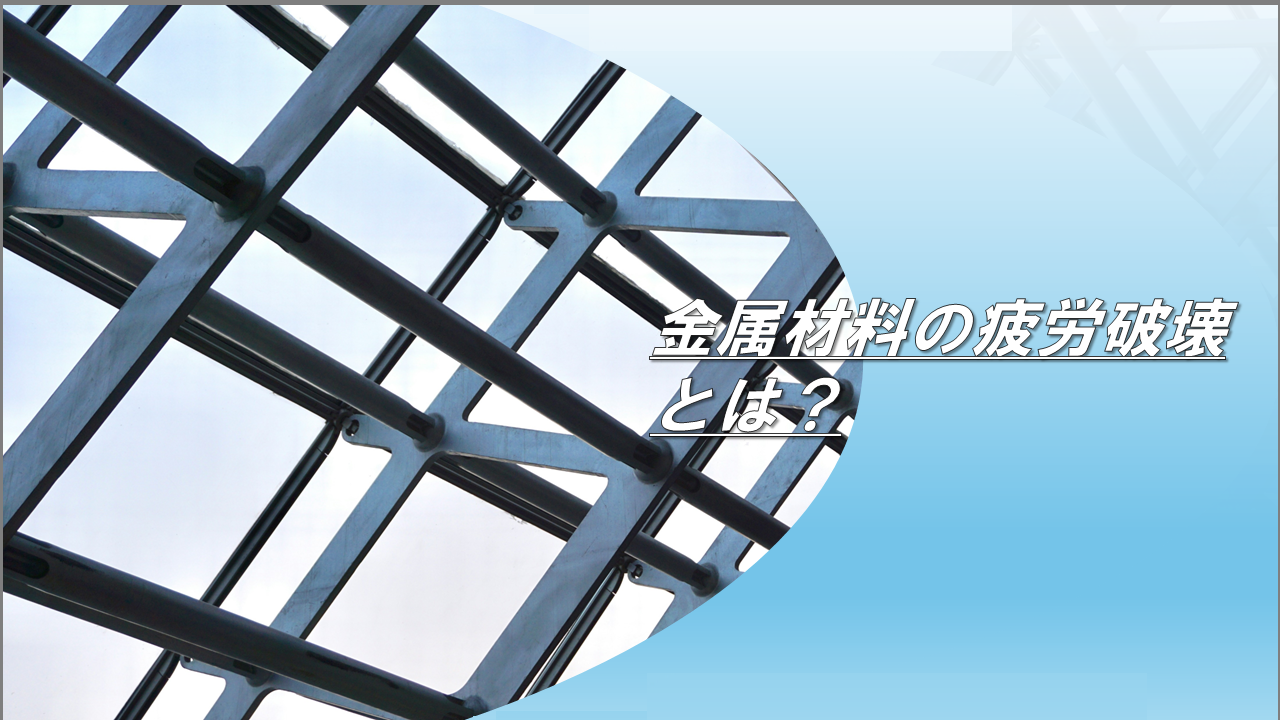
金属加工.comをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、山梨県・長野県にて切削加工やろう付けを行っている 北東技研工業株式会社 が運営しております。
金属加工に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
金属材料は、自動車や航空機、建築構造物など、日常生活から産業分野まで幅広く利用されています。しかし、金属は使用される環境や荷重条件によって、徐々に強度を失い、最終的に破壊に至ることがあります。その中でも特に注意すべき現象が「疲労破壊」です。疲労破壊は、外見上は損傷が少なくても、繰り返し荷重によって内部に微小な亀裂が発生し、やがて致命的な破壊に至る現象です。本記事では、金属材料の疲労破壊の基本概念から原因、評価方法、対策までわかりやすく解説します。
疲労破壊とは何か
疲労破壊とは、金属材料が長期間にわたって繰り返し荷重を受けることで発生する破壊現象です。重要なのは、荷重の大きさが材料の降伏強さや引張強さを下回っていても破壊が起こる点です。つまり、一度の荷重では破断しないような応力でも、繰り返し加わることで破壊が進行します。
疲労破壊の特徴
疲労破壊の特徴には以下のような点があります。
- 累積損傷型の破壊:材料は一度の荷重で壊れるのではなく、少しずつ損傷が蓄積して破壊に至る。
- 亀裂の進展が段階的:疲労亀裂は微小な亀裂として始まり、徐々に成長して最終的に材料を分断する。
- 表面から始まることが多い:応力集中が発生しやすい表面や切欠部で亀裂が発生するケースが多い。
- 特定の疲労限度が存在:一部の金属には、ある応力以下であれば理論上は疲労破壊が起きない「疲労限度」が存在する。
このような特徴から、疲労破壊は突然の破壊に見えても、実際には長期間にわたる微小亀裂の進展による累積現象であることが分かります。
疲労破壊のメカニズム
疲労破壊は複雑な現象ですが、一般的には「亀裂の発生」と「亀裂の進展」の2段階で説明されます。
亀裂の発生
繰り返し荷重が加わると、材料内部や表面に微小な変形が発生します。この変形は主に以下の原因で起こります。
- 応力集中:ネジの谷部や穴の周囲など、形状の不連続点で局所的に応力が高まる。
- 表面欠陥:加工傷や表面粗さにより局所的な応力集中が発生する。
- 内部欠陥:鋳造や溶接で生じた気泡、介在物などの不連続が亀裂の起点になる。
亀裂はこれらの応力集中点から発生し、通常は表面近くで始まります。初期段階の亀裂は非常に微小で、外見上はほとんど損傷が確認できません。
亀裂の進展
亀裂が発生すると、繰り返し荷重により亀裂先端で局所応力が高まり、亀裂は徐々に進展します。この進展速度は荷重の大きさや材料の性質によって変わります。
- 亀裂進展の段階:最初は非常に遅い進展速度ですが、亀裂が大きくなるにつれて進展速度が増加し、最終的に急激に破壊に至る。
- 応力集中の影響:亀裂先端の応力集中が進展速度を左右する。
- 環境要因:湿度や化学物質による腐食が亀裂進展を加速する場合もあります。
疲労破壊の過程では、微小亀裂の進展段階で早期発見できれば、大きな事故を防ぐことが可能です。
疲労破壊の分類
疲労破壊は荷重条件や材料の状態によっていくつかの種類に分類されます。
高周期疲労(HCF: High Cycle Fatigue)
- 繰り返し回数が10万回以上の領域で発生する疲労。
- 応力は比較的低く、弾性範囲内での荷重繰り返し。
- 自動車のシャーシや航空機の翼など、日常的に繰り返される低応力での破壊。
低周期疲労(LCF: Low Cycle Fatigue)
- 繰り返し回数が数百~数千回程度で発生。
- 応力が高く、塑性変形を伴う。
- 機械プレスや橋梁の荷重変動など、高応力環境での破壊。
繰返し応力疲労と腐食疲労
- 繰返し応力疲労:純粋に繰り返し荷重による疲労。
- 腐食疲労:湿度や化学薬品にさらされた環境で、腐食作用が亀裂進展を加速する疲労。
環境条件や荷重条件によって、同じ材料でも疲労寿命は大きく異なります。
疲労寿命とS-N曲線
疲労破壊の設計には「S-N曲線(応力-寿命曲線)」が広く用いられます。これは、ある応力レベルで材料が何回繰り返し荷重に耐えられるかを示す曲線です。
- 縦軸:応力(Stress)
- 横軸:繰返し回数(Number of cycles)
S-N曲線の特徴:
- 応力が高いほど、疲労寿命は短くなる。
- 一部の鋼材には、ある応力以下では疲労破壊が発生しない「疲労限度」が存在する。
- 曲線の形状から、設計上の安全余裕を確保できる。
S-N曲線は試験によって得られますが、設計段階では材料特性や荷重条件を考慮して安全マージンを見込むことが重要です。
疲労破壊の原因
疲労破壊はさまざまな要因が重なって発生します。
材料特性
- 硬さと靭性:硬く脆い材料は亀裂が発生しやすく、靭性の高い材料は亀裂進展に耐えやすい。
- 結晶構造や組織:粒界や介在物が応力集中点となる。
- 表面粗さ:加工や研磨の仕上げが不十分だと亀裂が発生しやすい。
設計上の要因
- 応力集中:穴、段差、溝など形状的不連続点。
- 荷重の方向:引張、圧縮、曲げ、ねじりなど荷重種類による亀裂進展の差。
- 繰返し回数:荷重の頻度やサイクル数。
環境要因
- 腐食や酸化:水分、塩分、化学物質による材料劣化。
- 温度変化:高温や低温により材料強度や靭性が変化。
- 湿度:湿潤環境で亀裂進展が加速。
これらの要因を総合的に考慮して設計や材料選定を行うことが、疲労破壊防止の鍵となります。
疲労破壊の評価方法
疲労破壊の評価は、材料選定や設計の安全性確認に不可欠です。代表的な方法は以下の通りです。
疲労試験
- 回転曲げ疲労試験:材料試験片を回転させて曲げ荷重を繰り返す。
- 引張圧縮疲労試験:引張・圧縮を交互に繰り返す荷重を材料に加える。
- 三点曲げ疲労試験:梁状の試験片を三点支持で繰返し曲げる。
これらの試験により、S-N曲線や疲労限度、亀裂進展速度などを把握できます。
非破壊検査
- 磁粉探傷(MT):鉄系材料の表面亀裂を磁粉で可視化。
- 浸透探傷(PT):液体浸透剤で表面亀裂を確認。
- 超音波探傷(UT):内部亀裂や欠陥を検出。
- X線検査(RT):内部の空洞や亀裂を画像化。
非破壊検査により、使用中の部品の亀裂進展を早期に発見することが可能です。
数値解析
- 有限要素法(FEM):応力分布や応力集中の評価。
- 累積損傷理論:繰返し荷重による損傷の進行を数値で予測。
- 亀裂進展解析:亀裂成長速度を解析して寿命を予測。
これらの手法を組み合わせることで、より現実的な疲労寿命の予測が可能です。
疲労破壊の防止対策
疲労破壊を防ぐためには、材料選定、設計、製造、保守点検など多方面で対策を講じる必要があります。
材料選定
- 靭性の高い材料を選ぶことで亀裂進展を抑制。
- 不純物や介在物の少ない高品質材料を使用。
設計上の工夫
- 応力集中を避けるために段差や穴の形状を丸める。
- 過大な荷重や曲げがかかる部位の補強。
- 安全率を確保した荷重設計。
表面処理
- 研磨やショットピーニングにより表面応力を圧縮状態にして亀裂発生を抑制。
- 防錆処理やコーティングで腐食を防止。
製造管理
- 溶接や熱処理工程の管理で内部欠陥を最小化。
- 機械加工後の残留応力管理。
保守・点検
- 定期的な非破壊検査による亀裂早期発見。
- 亀裂や欠陥が見つかった場合は早期交換や補修。
これらの対策を組み合わせることで、疲労破壊による事故やトラブルを未然に防ぐことができます。
疲労破壊の実例
疲労破壊は実際の工業製品や構造物で多くの事例があります。
- 航空機の翼や胴体:長時間の飛行で繰返し応力が加わり、亀裂進展が問題になる。
- 自動車のサスペンション部品:道路の凹凸による繰返し荷重で疲労破壊が発生。
- 橋梁や建築構造物:交通荷重や風荷重での繰返し応力により亀裂が進展。
- 機械の回転部品:ベアリングやシャフトでの繰返し曲げ応力による亀裂。
こうした事例からも、疲労破壊は安全性に直結する重大な現象であることがわかります。
まとめ
金属材料の疲労破壊は、繰返し荷重によって微小亀裂が発生・進展し、最終的に材料を破壊する現象です。外見上は損傷が分かりにくい場合でも、累積損傷として内部で進行しています。疲労破壊を理解し、防止するためには、材料選定、設計、製造、表面処理、保守点検のすべての工程で対策を講じる必要があります。S-N曲線や非破壊検査、数値解析といった評価手法を用いることで、疲労寿命の予測と安全性の確保が可能です。日常生活や産業における安全性を守るためには、疲労破壊の理解と対策が欠かせません。
いかがでしたでしょうか?
金属加工.comでは、他にも金属加工関連の情報を発信しております。他にも気になる記事がありましたら、是非ご覧ください。
金属加工.comのトップページはこちら↓

関連記事はこちら↓







