青銅の溶接・ろう付け技術
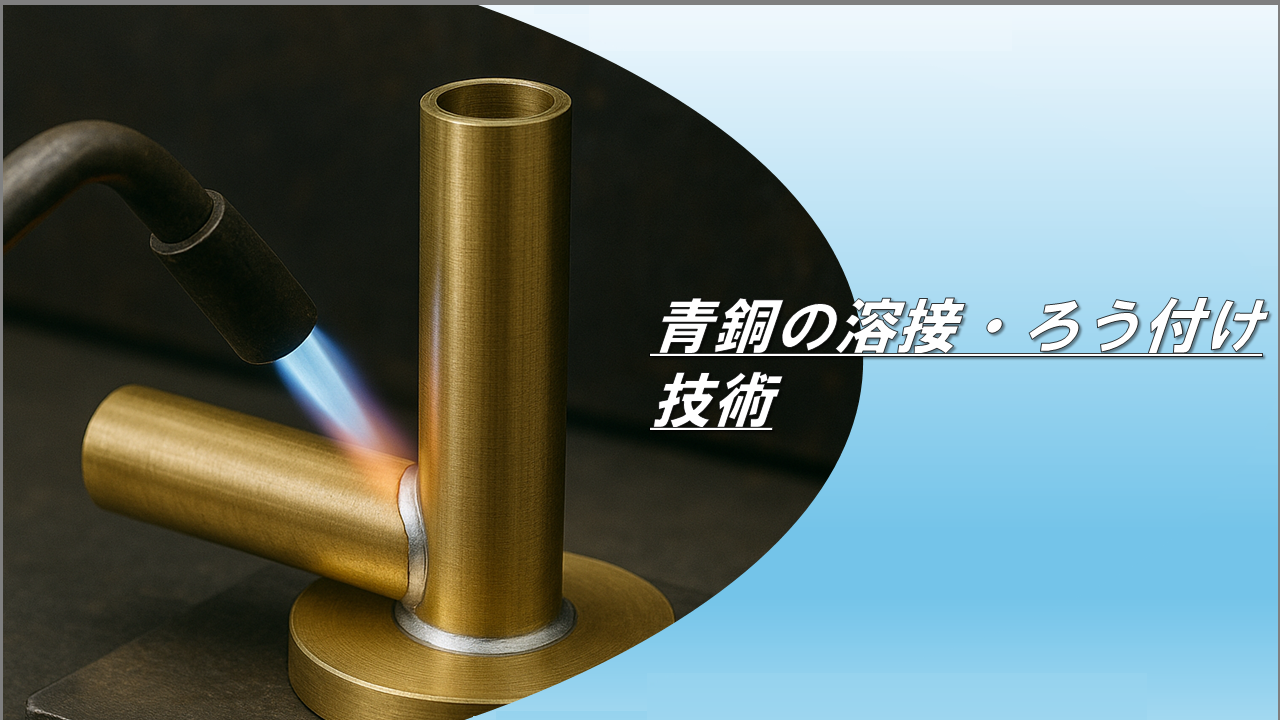
金属加工.comをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、山梨県・長野県にて切削加工やろう付けを行っている 北東技研工業株式会社 が運営しております。
金属加工に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
青銅は、古くから人類に利用されてきた合金であり、主に銅とスズをベースにした材料です。硬度や耐摩耗性に優れ、さらに耐食性も高いため、建築装飾、機械部品、楽器、船舶部材など幅広い分野で活用されています。しかし、青銅を接合する際には、鉄やアルミと比べて難易度が高いといわれます。理由としては、成分による溶融特性の違い、酸化皮膜の形成、熱伝導率の高さなどがあり、適切な技術を理解しなければ良好な接合は得られません。
本記事では、青銅の溶接とろう付けに焦点を当て、それぞれの特徴、適用範囲、作業上の注意点をわかりやすく解説します。
青銅の溶接技術
青銅の溶接の難しさ
青銅は銅を主成分としながらスズやリン、アルミニウムなどを含む合金です。そのため溶接時に以下のような課題が生じます。
- 熱伝導率が高い:熱が広がりやすく、アーク熱が分散して溶け込み不足が起きやすい。
- 酸化皮膜の形成:溶融時に強固な酸化皮膜ができ、溶接金属との濡れ性を妨げる。
- 脆性割れの危険性:特にスズ青銅は冷却過程で割れやすい。
これらを克服するためには、溶接方法や条件の選択が重要になります。
適した溶接方法
青銅の溶接にはいくつかの方法があります。
- TIG溶接(アルゴン溶接)
不活性ガスで酸化を防ぎつつアーク溶接を行う方法。薄板や小物部品の溶接に有効で、比較的仕上がりも良好。熱入力を制御しやすい点がメリットです。 - ガス溶接
古くから使われてきた方法で、青銅の修理や装飾品などに利用されます。酸素アセチレン炎を使用しますが、酸化防止のためフラックスを併用するのが一般的です。 - アーク溶接(被覆アーク)
厚板や構造物の補修に用いられることがあります。青銅専用の被覆アーク溶接棒を選ぶ必要があり、溶接部は硬くなる傾向があります。 - 電子ビーム溶接・レーザー溶接
精密機器や高精度を要求される場面で使用。装置コストは高いですが、溶け込み制御や変形抑制に優れています。
溶接条件と注意点
- 予熱の活用:青銅は熱伝導が高いため、溶接前に200~400℃程度に予熱すると溶け込みが安定します。
- 後熱処理:冷却時のひび割れ防止のため、徐冷や応力除去焼鈍を行うことがあります。
- シールドガス:TIG溶接では高純度アルゴンを使用。必要に応じてヘリウム混合ガスを利用すると熱効率が改善します。
- 溶加材の選定:母材と近い成分を持つ溶加棒を使うことで割れを抑制できます。
このように、青銅の溶接には高度な知識と経験が必要ですが、適切な条件を整えれば強固で美しい仕上がりを得ることが可能です。
青銅のろう付け技術
ろう付けの特徴
ろう付けは、母材自体を溶かすのではなく、融点の低い「ろう材」を溶かして接合する方法です。青銅においては、溶接に比べて次のような利点があります。
- 低温で処理できるため、母材への熱影響が少ない。
- 薄板や細かい部品でも精密に接合可能。
- 美観を損なわずに仕上げられる。
これらの特徴から、青銅製の美術品、楽器、配管部品などに広く利用されています。
適したろう材
青銅のろう付けには以下の種類のろう材が用いられます。
- 銀ろう:青銅との濡れ性が良く、強固な接合が可能。特に薄物や高強度が必要な部品に適しています。
- 銅ろう:コストを抑えられるが、流動性や接合強度はやや劣ります。大きな部品の補修などに用いられます。
- 黄銅ろう:銅-亜鉛系のろう材で、装飾用途や一般的な青銅製品に利用されます。
用途に応じてろう材を選び、フラックスを併用するのが一般的です。
ろう付けプロセス
- 表面処理:酸化皮膜や油分を取り除き、ろう材の濡れ性を高めます。サンドブラストや酸洗いが有効です。
- 組み立て・仮固定:適切な隙間(0.05~0.2mm程度)を設けることで、毛細管現象によるろうの流動がスムーズになります。
- フラックス塗布:酸化膜を除去し、ろうの広がりを助けるために必須。
- 加熱:トーチや炉を用いて加熱。加熱温度はろう材の種類により異なりますが、通常600~800℃程度。
- 冷却・仕上げ:急冷は避け、自然冷却を基本とします。フラックス残渣は腐食の原因になるため、洗浄して取り除きます。
ろう付けの注意点
- 隙間が狭すぎるとろうが浸透しない。広すぎると強度不足になる。
- フラックス残りは必ず除去すること。特に美術品や装飾品では外観を大きく損なう。
- 異種金属とのろう付けでは、電食のリスクを考慮する必要がある。
溶接とろう付けの使い分け
青銅を接合する際には、目的や条件によって溶接とろう付けを使い分けることが重要です。
- 強度重視・厚物 → 溶接が適する。
- 精密・薄物・美観重視 → ろう付けが適する。
- 修理・補修 → どちらも可能だが、ひび割れのリスクがある場合はろう付けが有利。
たとえば、船舶部品や重機部材の修理には溶接が多用されますが、楽器や装飾品ではほとんどがろう付けです。
実務におけるポイント
- 溶接では予熱・後熱を丁寧に行い、割れを防止する。
- ろう付けでは接合部の前処理とフラックス管理が品質を左右する。
- いずれも母材と近い成分を持つ補助材料を選定することで、強度と耐久性を確保できる。
- 青銅特有の熱伝導率の高さを理解し、加熱バランスを意識する。
まとめ
青銅の接合は、鉄やステンレスと比べると難易度が高い分、確かな技術が求められます。溶接では熱管理と溶加材の選定、ろう付けでは表面処理と毛細管現象の活用が成功の鍵となります。
適切な方法を選び、手順を守ることで、青銅の美しさと機能を損なわずに長期にわたり使用できる部品や製品を作り出すことが可能です。
いかがでしたでしょうか?
金属加工.comでは、他にも金属加工関連の情報を発信しております。他にも気になる記事がありましたら、是非ご覧ください。
金属加工.comのトップページはこちら↓

関連記事はこちら↓







