真鍮と青銅の電気伝導率の違い
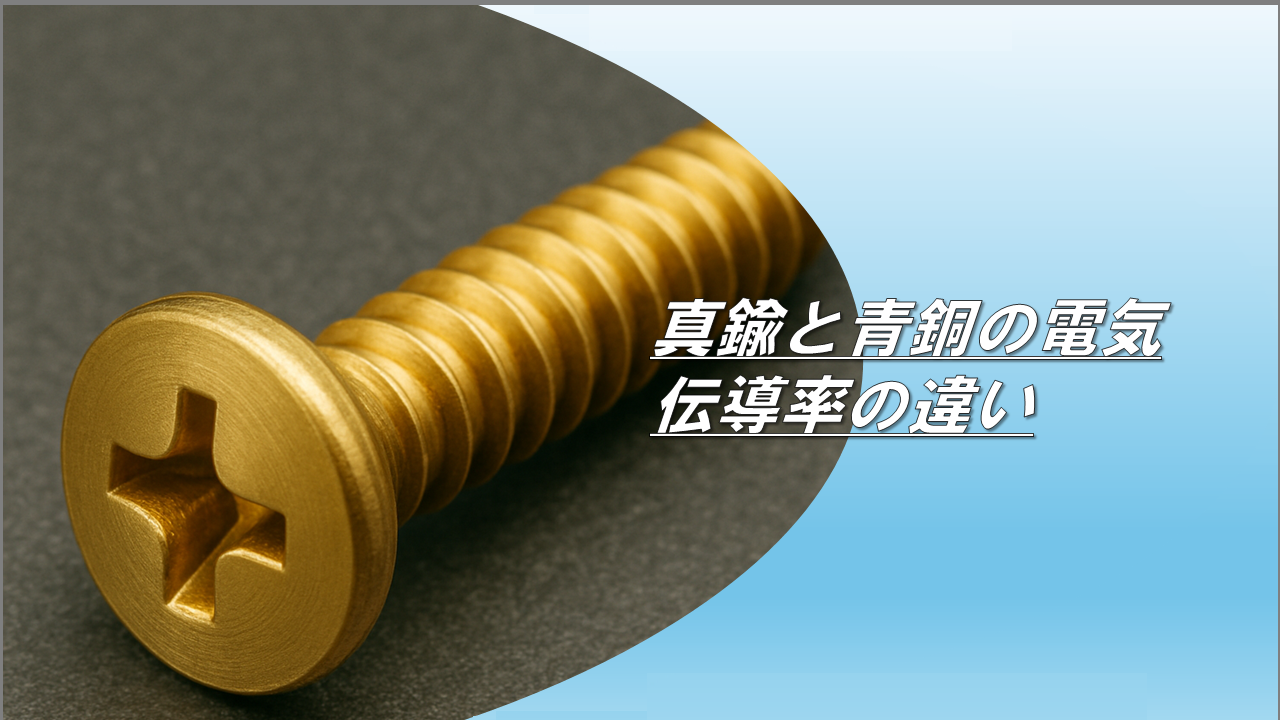
金属加工.comをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、山梨県・長野県にて切削加工やろう付けを行っている 北東技研工業株式会社 が運営しております。
金属加工に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
金属は私たちの生活のあらゆる場面で利用されており、その特性の一つとして「電気伝導率」が重要な役割を果たします。電気伝導率とは、金属がどの程度電気を流しやすいかを示す指標であり、電子部品や電線、さらには工業材料の選定において欠かせない性能値です。本記事では、古くから広く利用されてきた合金である「真鍮」と「青銅」を取り上げ、それぞれの電気伝導率の特徴や違いについて詳しく解説していきます。
真鍮と青銅とは
まず、両者がどのような合金であるかを整理しておきましょう。真鍮(しんちゅう)は銅と亜鉛を主成分とする合金で、一般的には銅を60〜70%、亜鉛を30〜40%程度含みます。色調は黄金色に近く、加工性や装飾性に優れるため、建築材や楽器、装飾品などに用いられます。また、機械部品やネジなどの工業的用途にも広く使われています。
一方、青銅(せいどう)は銅と錫を主成分とする合金で、銅を80〜90%、錫を10〜20%程度含むのが一般的です。古代から鋳造に利用されてきた歴史ある合金で、硬度や耐摩耗性に優れ、彫刻、仏像、貨幣、機械部品などに広く用いられてきました。近代以降は、錫以外にもアルミニウムやリンなどを添加した「特殊青銅」も開発され、多様な特性を持つ材料へと発展しています。
電気伝導率とは何か
電気伝導率とは、物質中を電子がどれだけスムーズに移動できるかを示す値です。単位は「シーメンス毎メートル(S/m)」で表され、数値が大きいほど電気を良く流します。最も代表的な導体は銅であり、国際的には銅の電気伝導率を100%(IACS値=International Annealed Copper Standard)として基準化されています。
例えば、純銅の電気伝導率はおよそ5.96×10^7 S/mであり、これは金属の中でも非常に高い値です。これに対し、銅に他の元素を添加して作られる合金は、添加元素の影響により結晶格子に乱れが生じ、電子の移動が妨げられるため、純銅よりも伝導率は低下します。真鍮や青銅もその典型例です。
真鍮の電気伝導率
真鍮の電気伝導率は、銅の含有量と亜鉛の比率によって大きく変化します。一般的な黄銅(Cu:60〜70%、Zn:30〜40%)では、銅に比べて大幅に電気伝導率が下がり、IACSで20〜30%程度、すなわち1.0×10^7〜1.7×10^7 S/m程度となります。
これは、銅に亜鉛を加えることで結晶構造に乱れが生じ、電子の散乱が増えるためです。結果として純銅のような優れた導電性は失われます。そのため真鍮は、電線や高導電性が必要な電子部品には用いられず、むしろ機械的強度や耐食性、加工性といった性質を活かした用途に利用されます。
ただし、真鍮にも種類があり、亜鉛含有量が少ない「高銅黄銅」では伝導率がやや高めに保たれます。逆に亜鉛が多くなると導電性はさらに低下し、場合によっては10%程度まで落ち込むこともあります。
青銅の電気伝導率
青銅もまた、銅に錫を加えることで特性が変化する合金です。一般的な錫青銅(Cu:80〜90%、Sn:10〜20%)の電気伝導率は、IACSでおおよそ10〜15%程度、すなわち0.6×10^7〜0.9×10^7 S/mの範囲に収まります。真鍮よりもさらに低い値であることが多く、電気を流す材料としては不利といえます。
錫の添加によって結晶格子に強い乱れが生じるため、電子が移動する際の散乱が大きくなることが原因です。このため、青銅は電気を通すよりもむしろ機械的強度や耐摩耗性、耐食性が重視される用途に適しています。例えば、軸受け、バルブ部品、コイン、芸術品などで広く利用されています。
なお、アルミ青銅やリン青銅などの特殊青銅は、成分によって導電率が変わりますが、いずれにしても純銅には及びません。
真鍮と青銅の比較
両者を比較すると、電気伝導率の面では真鍮の方がやや優れているといえます。典型的な値を整理すると以下のようになります。
- 純銅:IACS 100%(約5.96×10^7 S/m)
- 真鍮:IACS 20〜30%(約1.0×10^7〜1.7×10^7 S/m)
- 青銅:IACS 10〜15%(約0.6×10^7〜0.9×10^7 S/m)
この数値からも分かるように、青銅は真鍮に比べてもさらに導電性が低く、電気用途よりも機械的特性や装飾性を重視する分野で選ばれます。
なぜ導電率が異なるのか
導電率の違いを生む最大の要因は「合金化による電子散乱」です。純銅の結晶格子は整然としており、自由電子がスムーズに移動できます。しかし、そこに亜鉛や錫といった異なる元素が加わると、原子半径や電気的性質の違いから結晶格子に歪みが生じ、電子の通り道に障害が生まれます。
特に錫は銅との格子不整合が大きいため、青銅は真鍮よりも強く電子散乱を引き起こし、結果として導電性が低くなるのです。このため、青銅は耐摩耗性や硬さを得る代わりに、電気的性質は犠牲にしているといえます。
用途における違い
電気伝導率の違いは、両者の利用分野の違いにもつながっています。真鍮は青銅より導電率が高いため、電気的接点や端子などに使われる場合があります。特に強度と導電性のバランスが必要な部品に適しています。一方、青銅は導電性が低いため、電気部品としての利用は限定的で、主に耐摩耗性を生かした軸受けや機械部品に用いられます。
このように、真鍮と青銅は同じ銅合金でありながら、その伝導率の違いによって用途が明確に分かれているのです。
まとめ
真鍮と青銅はどちらも銅をベースとした合金ですが、添加元素である亜鉛と錫の違いによって電気伝導率に大きな差が生まれます。真鍮はIACS 20〜30%と比較的高い導電性を持ち、電気部品にも一定の用途があります。これに対して青銅はIACS 10〜15%程度と低く、電気的な利用は少なく、むしろ強度や耐食性を活かした部品に適しています。
両者の特性を理解することで、材料の選定や設計において適材適所を判断することができます。電気伝導率という視点で見たとき、真鍮と青銅は似て非なる合金であり、現代の工業においてそれぞれの持ち味を発揮しているといえるでしょう。
いかがでしたでしょうか?
金属加工.comでは、他にも金属加工関連の情報を発信しております。他にも気になる記事がありましたら、是非ご覧ください。
金属加工.comのトップページはこちら↓

関連記事はこちら↓







