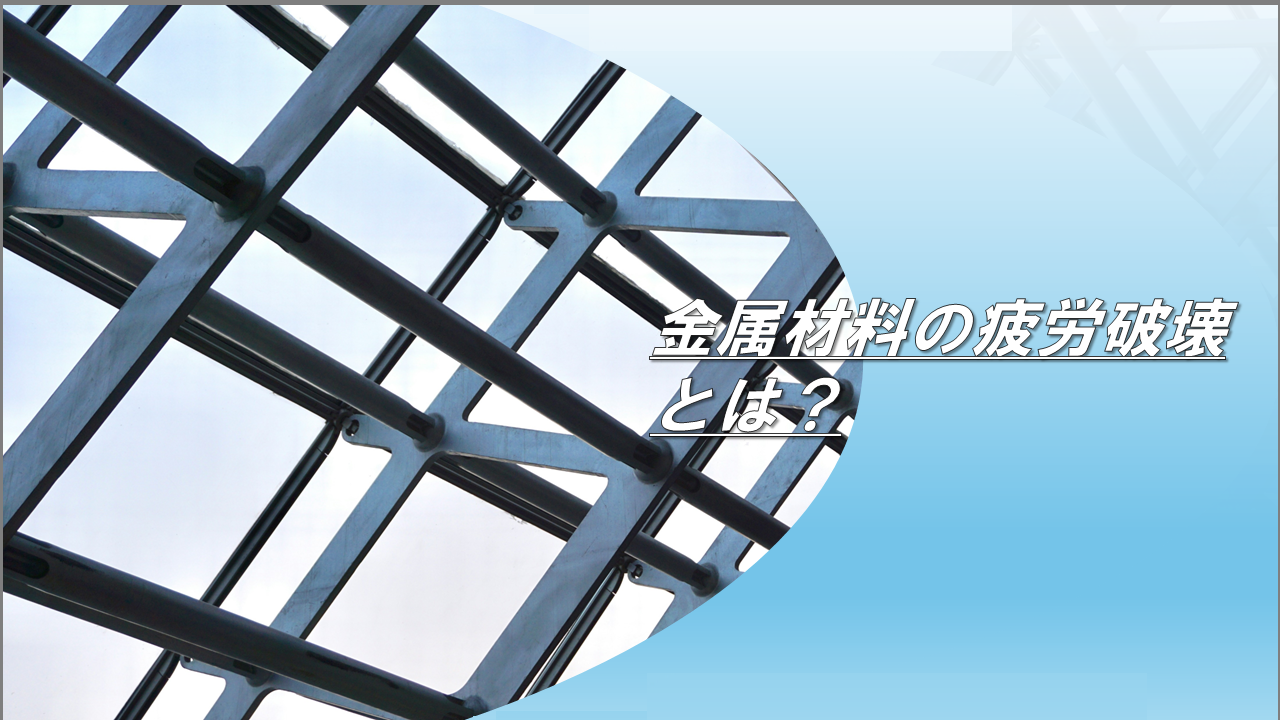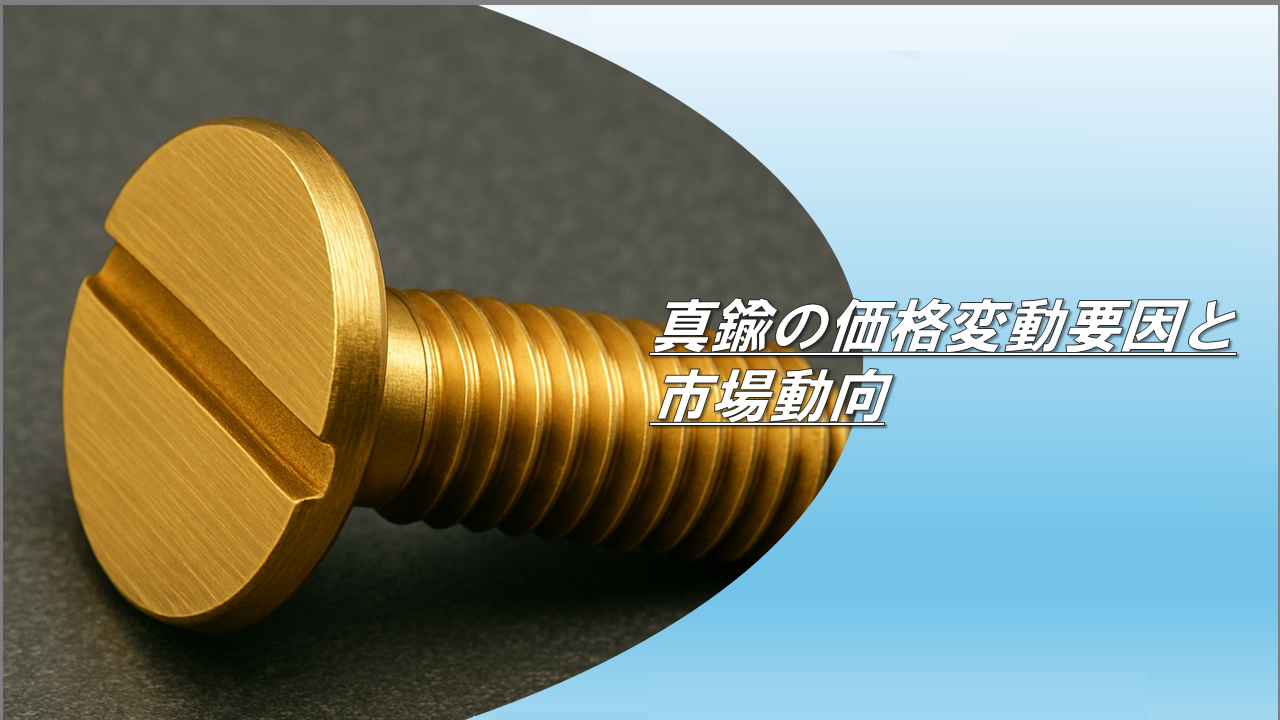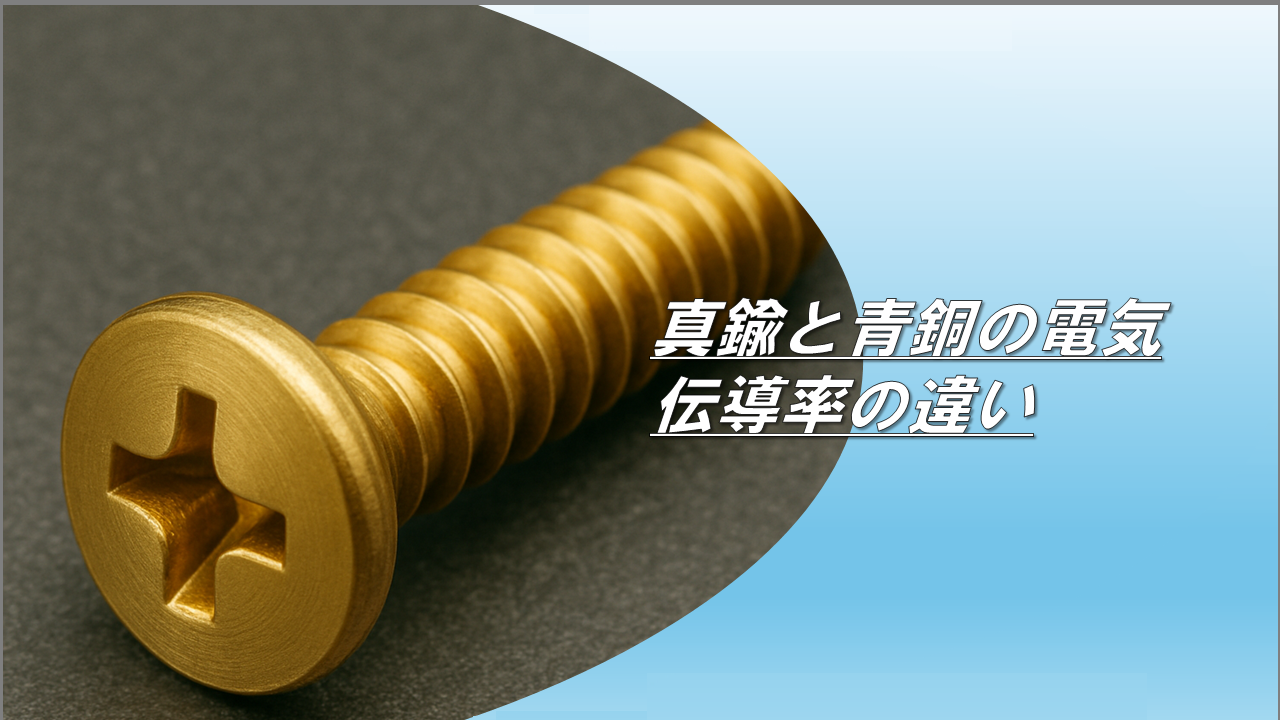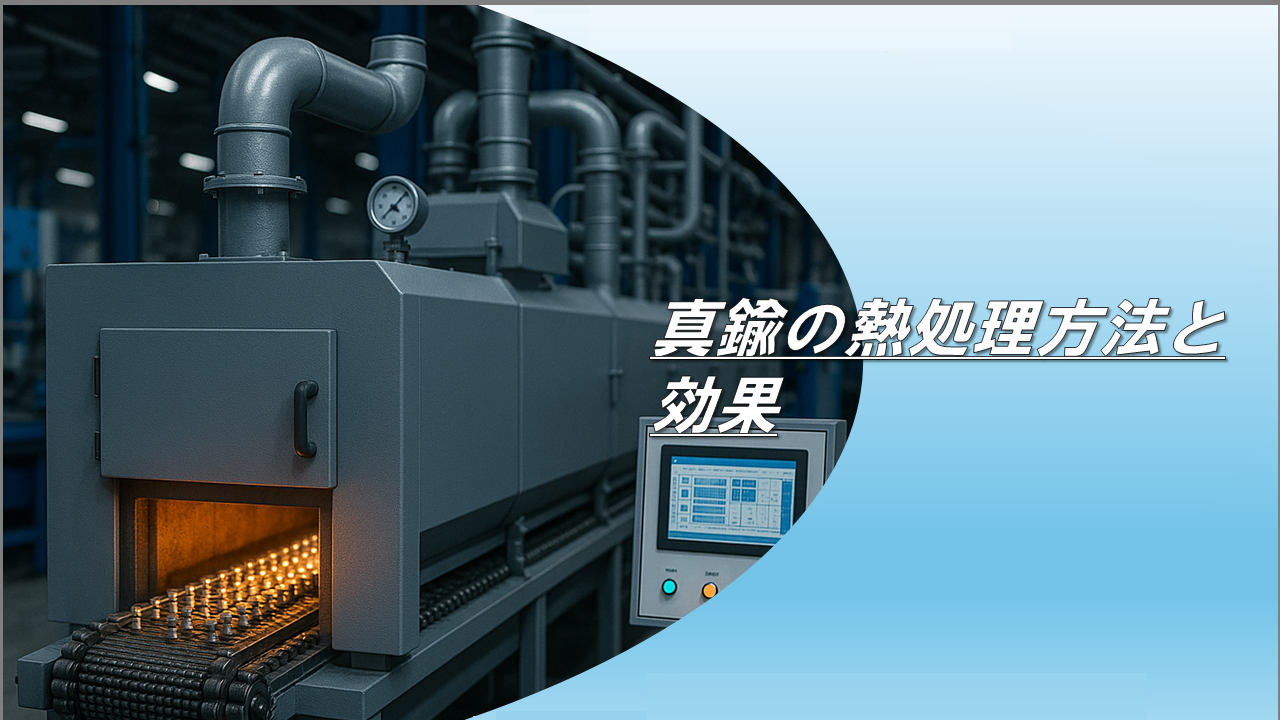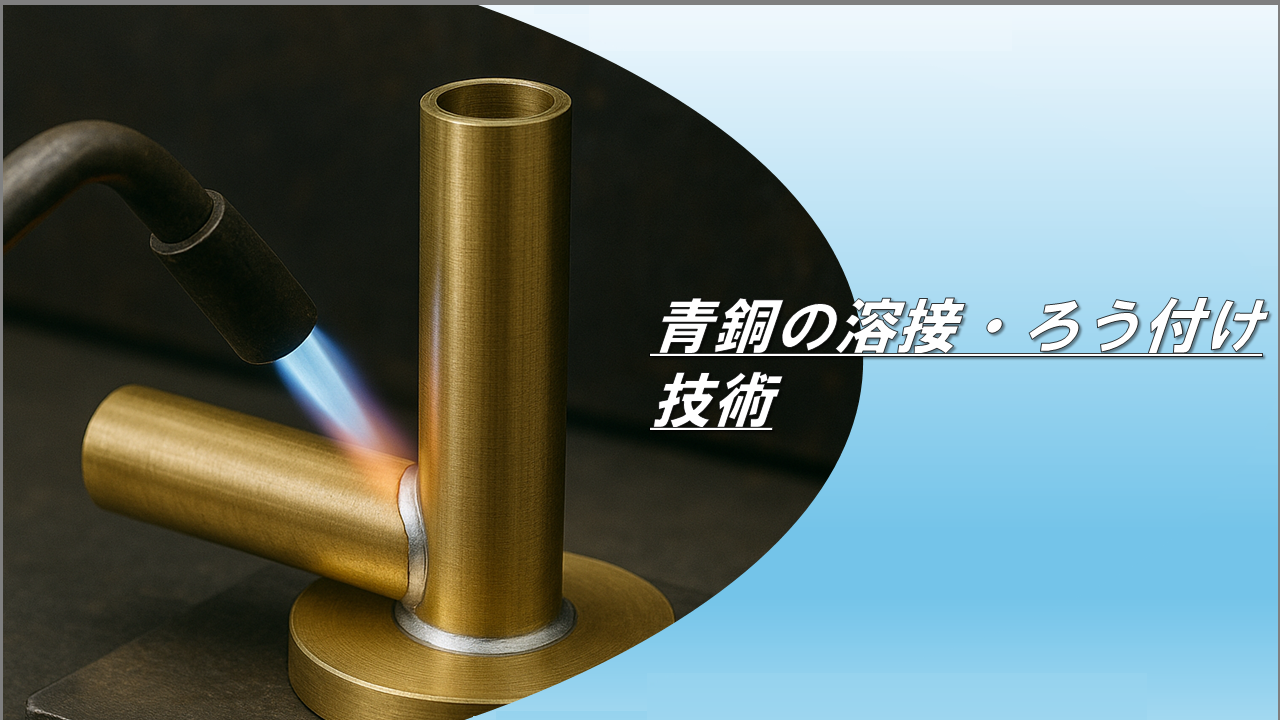鍍金加工の基本工程と各ステップのポイント

金属加工.comをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、山梨県・長野県にて切削加工やろう付けを行っている 北東技研工業株式会社 が運営しております。
金属加工に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
鍍金加工とは
鍍金(ときん、めっき)加工は、金属表面に他の金属を被覆することで、耐食性や装飾性、導電性、耐摩耗性などの特性を向上させる重要な表面処理技術です。電子機器、自動車、建築資材、アクセサリーなど、さまざまな分野で広く利用されています。本稿では、鍍金加工の基本工程を順を追って解説し、各ステップでの重要なポイントについて詳述します。
前処理工程
鍍金加工の品質を左右する最も重要なステップが前処理です。前処理の目的は、鍍金する母材(金属基材)の表面から汚れや酸化膜、油分などの不純物を除去し、鍍金層の密着性を高めることです。前処理は複数の工程から構成され、以下のようなプロセスが含まれます。
・脱脂処理:油脂類の除去。アルカリ性洗浄液や有機溶剤を用いて行います。
・水洗:脱脂剤や不純物を完全に洗い流すための純水洗浄。
・酸洗い(エッチング):金属表面の酸化膜やスケールを除去。硫酸や塩酸などの酸を使用します。
・活性化処理:表面を化学的に活性化して、次工程の鍍金液との反応性を向上させます。
前処理工程で不備があると、鍍金不良(ピンホール、剥離、ムラなど)につながるため、各工程での洗浄効果の確認と徹底した品質管理が求められます。
下地鍍金工程
本鍍金の前に、下地鍍金を施すことが一般的です。これは母材との密着性を高め、本鍍金の品質を向上させるためのステップです。下地鍍金には、銅、ニッケル、亜鉛などが用いられます。
・銅メッキ:導電性が高く、上塗り鍍金の密着性を向上。
・ニッケルメッキ:耐食性、耐摩耗性が高く、中間層として多用されます。
・亜鉛メッキ:防錆目的で使用され、鉄鋼製品によく施されます。
下地鍍金の選定は、最終製品の用途や要求される性能によって異なります。たとえば電子部品では導電性が重視されるため銅鍍金が多く、自動車部品では耐食性からニッケル鍍金が選ばれることが多いです。
本鍍金工程
本鍍金工程では、製品に必要な特性を持つ金属を選定して被覆します。代表的な鍍金種には以下のようなものがあります。
・金メッキ(Au):高い導電性と耐腐食性、美観を備え、電子部品や高級装飾品に使用。
・銀メッキ(Ag):導電性と熱伝導性が高く、接点や端子に多用。
・クロムメッキ(Cr):硬度が高く、耐摩耗性・耐熱性・美観に優れる。自動車部品や水道金具に使用。
・スズメッキ(Sn):食品関連部品に使用され、無害で耐食性がある。
本鍍金では、鍍金液の濃度、温度、電流密度、pH値などの条件管理が極めて重要です。これらの条件が適正でないと、鍍金層の厚みが不均一になったり、表面に欠陥が生じたりする可能性があります。
後処理工程
鍍金後の後処理は、鍍金層の保護や性能の安定化を目的として行われます。主な後処理工程には以下があります。
・パッシベーション(不動態化処理):酸化防止や耐食性向上のため、化学薬品で処理。
・乾燥処理:水分を完全に除去することで腐食のリスクを軽減。
・焼きなまし処理(ベーキング):水素脆化防止のために高温で加熱処理(特に高張力鋼など)。
・外観検査
・膜厚検査:目視や専用機器を用いて品質を確認。
これらの工程を適切に行うことで、製品の寿命や機能性を向上させることができます。
品質管理と環境配慮
鍍金加工は精密な工程であり、厳密な品質管理が求められます。膜厚の均一性、密着性、外観の均一性などが評価基準となり、電気測定機器やSEM(走査電子顕微鏡)などを用いた検査が行われます。
また、環境への配慮も不可欠です。鍍金工程で使用される薬品には有害物質が含まれる場合があるため、排水処理設備の整備、使用薬品の低毒化、工程内リサイクルの導入などが進められています。特にRoHS指令やREACH規制などの国際的な環境規制に対応するため、鉛フリー鍍金や六価クロムを含まない処理技術の導入が進んでいます。
鍍金加工の応用事例
鍍金技術はさまざまな産業分野で活用されています。
- 自動車:エンジン部品やシャーシの防錆、装飾メッキに活用。
- 電子機器:基板や端子、ICパッケージに高精度な金・銀メッキが施されます。
- 医療:耐腐食性・生体適合性を生かしたインプラントや医療器具の表面処理に。
- 航空宇宙:高温・高圧環境に耐えるニッケル系合金の鍍金加工。
【まとめ】
鍍金加工は、前処理から後処理までの一連の工程を高い精度で管理することで、高品質な製品を生み出すことができます。各ステップでの注意点や品質管理の徹底が、最終的な製品の性能と信頼性を左右します。今後も新しい材料や環境規制への対応が進む中で、鍍金技術の進化が期待されます。また、無電解めっき技術やナノテクノロジーとの融合により、より高機能な表面処理が実現されることで、さらなる産業応用が広がることでしょう。
いかがでしたでしょうか?
金属加工.comでは、他にも金属加工関連の情報を発信しております。他にも気になる記事がありましたら、是非ご覧ください。
金属加工.comのトップページはこちら↓

関連記事はこちら↓