ろう付けの温度帯:軟ろうと硬ろうの違い
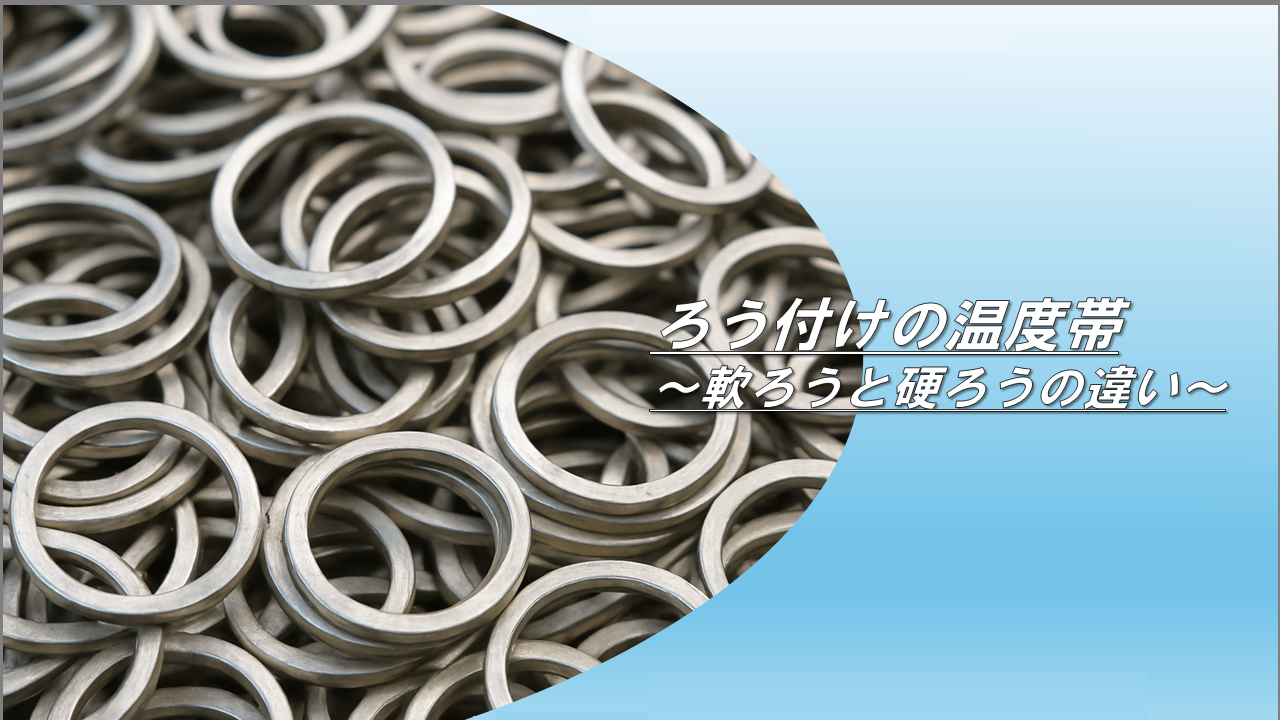
金属加工.comをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、山梨県・長野県にて切削加工やろう付けを行っている 北東技研工業株式会社 が運営しております。
金属加工に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
金属加工の中でも「ろう付け(brazing/soldering)」は、金属同士を強固かつ精密に接合できる優れた技術です。母材を溶融させることなく、比較的低温で作業できることから、部品の変形を防ぎつつ強度の高い接合が可能です。
ろう付けは大きく分けて「軟ろう」と「硬ろう」に分類され、両者の最大の違いは使用する**ろう材の融点(温度帯)**にあります。この記事では、軟ろう・硬ろうそれぞれの特徴、ろう材の種類と用途、接合に用いられる温度範囲、選定のポイントなどについて詳細に解説します。
ろう付けの分類:温度による違い
ろう付けは以下のように、ろう材の融点を基準に分類されます。
| 種類 | ろう材の融点 | 一般的な作業温度 | 主な用途例 |
|---|---|---|---|
| 軟ろう | 約450℃未満 | 180〜400℃前後 | 電子部品、配管、家庭用品など |
| 硬ろう | 約450℃以上 | 600〜1200℃ | 自動車部品、航空部品、工具など |
この450℃という境界は、JISやISOをはじめとする国際規格でも共通して用いられる基準です。ろう材の融点が450℃未満であれば軟ろう、450℃以上であれば硬ろうに分類されます。
軟ろう付け:特徴と主なろう材
特徴
軟ろう付けは比較的低温で行えるため、熱による母材の変形が抑えられ、電子部品や薄板、装飾品の接合などに適しています。また、加熱手段も簡易なもので済むため、はんだごてやホットプレートなどでも対応可能です。
使用される主なろう材とその詳細
軟ろう付けに使用されるろう材は「はんだ」とも呼ばれ、主成分にスズ(Sn)を用いた合金が多く使用されます。以下に代表的な軟ろう材を紹介します。
| ろう材名 | 主成分構成 | 融点 | 特徴・用途 |
|---|---|---|---|
| Sn-Pb(鉛入りはんだ) | Sn:63%、Pb:37% | 約183℃ | 電子部品に多用されたが、現在はRoHS規制により減少 |
| Sn-Ag-Cu(SACはんだ) | Sn:96.5%、Ag:3%、Cu:0.5% | 約217℃ | 鉛フリーはんだの代表格。電子機器での標準仕様 |
| Sn-Zn | Sn:91%、Zn:9% | 約198℃ | 安価だが酸化しやすく取り扱いに注意が必要。アルミとの接合に使われることも |
| Sn-Bi(スズ-ビスマス) | Sn:58%、Bi:42% | 約138℃ | 低温で融けるため熱に弱い部品や樹脂部品周辺での使用に適する |
| Sn-Cu | Sn:99.3%、Cu:0.7% | 約227℃ | 銅との相性が良く、配線やケーブルの接合に適している |
| In-Sn(インジウムはんだ) | In:52%、Sn:48% | 約120℃ | 低温対応や柔軟性重視、ガラスとの接合など特殊用途に使用 |
これらの合金は、使用する母材との親和性、フラックスの種類、電子部品への影響などを総合的に考慮して選定されます。特に鉛フリーはんだ(SAC)は、RoHS(特定有害物質使用制限)に対応した製品であり、現代の電子機器製造においては標準となっています。
硬ろう付け:特徴と主なろう材
特徴
硬ろう付けは、軟ろうよりも高温で行うため、強度・耐熱性に優れる接合が可能です。母材同士の接合強度が高く、長期間の使用に耐えうる構造部品に広く用いられます。接合にはトーチ、電気炉、誘導加熱、真空炉、雰囲気炉などが用いられます。
主なろう材と詳細
硬ろう材には多様な金属系合金が存在し、以下のように分類されます。
銀ろう(Ag系)
| 名称 | 主成分構成 | 融点範囲 | 特徴・用途 |
|---|---|---|---|
| Ag-Cu-Zn | Ag:45%、Cu:30%、Zn:25% | 約650〜750℃ | ステンレスや鉄鋼、銅などとの接合に対応。高強度。 |
| Ag-Cu-P | Ag:15%、Cu:80%、P:5% | 約720〜780℃ | 銅配管の接合に使われる。リンによる自助フラックス効果あり。 |
| Ag-Pd系 | Ag+Pd+Cuなど | 約720〜820℃ | 医療機器や電子部品など高信頼性用途に使用 |
銅ろう(Cu系)
| 名称 | 主成分構成 | 融点範囲 | 特徴・用途 |
|---|---|---|---|
| Cu-P | Cu:93%、P:7% | 約710〜880℃ | 銅との接合に優れる。空調・冷却配管に使用。酸化しやすいがフラックス不要。 |
| Cu-Zn系 | Cu:60%、Zn:40% | 約900℃前後 | 高温部材に対応。コスト安。鉄鋼用に適するが酸化に注意。 |
ニッケルろう(Ni系)
| 名称 | 主成分構成 | 融点 | 特徴・用途 |
|---|---|---|---|
| Ni-Cr-B-Si | Ni+Cr+Si+B | 約950〜1150℃ | 高温耐性に優れ、タービン、ジェットエンジンなどに使用される |
| Ni-P | Ni:88%、P:12% | 約875〜890℃ | 低温で流動性が良好。真空ろう付けに対応。電子部品や真空機器向け |
アルミろう(Al系)
| 名称 | 主成分構成 | 融点 | 特徴・用途 |
|---|---|---|---|
| Al-Si | Al:88%、Si:12% | 約577℃ | アルミニウム同士の接合に使用。熱伝導部品やヒートシンクに対応。 |
その他特殊合金ろう材
| ろう材名 | 用途・特徴 |
|---|---|
| 金ろう(Au系) | 医療機器や航空宇宙産業など極めて高い耐食性・信頼性が要求される用途。融点は950℃前後。高価。 |
| チタンろう | チタンやニオブなど高融点金属との接合。真空環境での使用が多い。 |
ろう材選定のポイント
適切なろう材を選ぶためには、以下の観点が重要です。
- 母材との親和性:ろう材が母材によく濡れ、強く付着するか。
- 使用温度帯:使用環境が高温か低温かに応じて選定。
- 接合強度:構造用途か、単なる電気的導通目的か。
- フラックスの有無:リン系ろう材などはフラックスなしでも可。
- 環境規制対応:RoHSやREACHなどに適合しているか。
- コスト・作業性:使用環境に合ったコストパフォーマンスが得られるか。
おわりに
ろう付けは、融点の異なる「軟ろう」と「硬ろう」に大別され、それぞれが異なる用途、目的、技術要件に応じて使い分けられています。使用するろう材は、合金の組成によって性能が大きく異なり、接合の成否や製品寿命に直結するため、慎重な選定が必要です。
まとめ
- 融点450℃を境に軟ろう(低温)と硬ろう(高温)に分類。
- 軟ろうではSn系はんだが主流、硬ろうではAg、Cu、Ni、Al系が用いられる。
- ろう材の選定は、接合目的、母材、温度条件、環境規制を考慮して行う。
- 現代ではフラックスレスや鉛フリー、真空ろう付けなど環境対応技術も進展。
将来的にはさらなる接合強度向上、プロセスの自動化、省エネ化が期待されており、ろう材の研究開発も進化を続けています。
いかがでしたでしょうか?
金属加工.comでは、他にも金属加工関連の情報を発信しております。他にも気になる記事がありましたら、是非ご覧ください。
金属加工.comのトップページはこちら↓

関連記事はこちら↓







