鉄の鍍金後に発生する白錆・赤錆の原因と対策
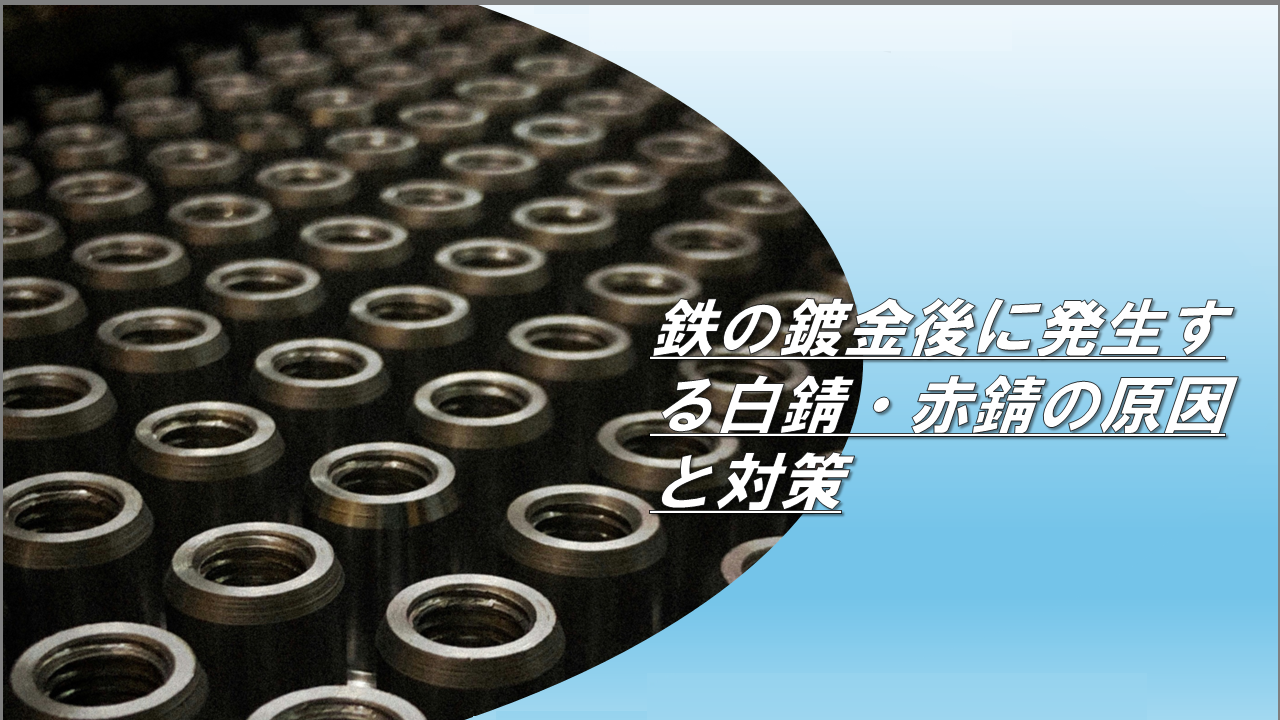
金属加工.comをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、山梨県・長野県にて切削加工やろう付けを行っている 北東技研工業株式会社 が運営しております。
金属加工に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
鉄は安価で強度に優れる一方、非常に錆びやすい金属です。そのため、表面にめっきを施して防錆性を高めることが一般的に行われています。しかし、めっきをしても使用環境や保管条件が悪いと「白錆」や「赤錆」が発生してしまうことがあります。この記事では、鉄の鍍金後に発生する白錆・赤錆の原因とその対策について、できるだけわかりやすく解説します。
白錆と赤錆の違い
白錆とは
白錆(しろさび)は、主に「亜鉛めっき(溶融亜鉛めっきや電気亜鉛めっき)」の表面に発生する白色の粉状腐食物です。見た目は白っぽい粉のようで、一見すると埃や汚れのように見えますが、これは亜鉛が酸化して生成された「酸化亜鉛(ZnO)」や「水酸化亜鉛(Zn(OH)₂)」です。
白錆は鉄ではなく、亜鉛層が腐食している状態を示しています。つまり、めっき層の犠牲防食作用が働いている途中段階といえますが、放置すると腐食が進み、最終的には鉄素地まで影響が及ぶ可能性があります。
赤錆とは
赤錆(あかさび)は、鉄が酸化して生じる赤褐色の錆で、主成分は酸化鉄(Fe₂O₃)です。
めっきによって守られていた鉄の表面が露出し、水分や酸素が直接触れることで発生します。赤錆が発生すると腐食が進行し、構造強度の低下や外観不良を引き起こします。
白錆が発生する主な原因
湿気の多い環境
白錆は、水分が付着したままの状態で空気中の二酸化炭素や酸素と反応して生じます。特に、湿度が高く結露しやすい環境や、雨に濡れた後に乾燥しにくい状態が続くと、白錆が急速に発生します。
密閉状態での保管
亜鉛めっき部品を密閉した状態で保管すると、空気の流れが悪くなり、内部の湿気が逃げにくくなります。これにより局所的な水膜が形成され、白錆の発生が促進されます。特に梅雨時期や、通気性の悪い梱包材を使用している場合は注意が必要です。
酸性ガス・塩分の影響
酸性ガス(SO₂、NOₓなど)や塩分(NaClなど)が付着すると、めっき表面の保護皮膜が破壊されやすくなり、白錆が生じやすくなります。海沿いの地域や、工場の排気ガスが多い場所では、環境腐食のリスクが高まります。
めっき処理後の乾燥不足
めっき後の洗浄水が完全に乾燥していない状態で梱包したり、保管したりすると、残留水分が腐食反応を引き起こします。特に電気亜鉛めっきでは、洗浄水に微量の塩素や硫酸イオンが残ると、白錆発生の引き金になります。
赤錆が発生する主な原因
めっき層の損傷
機械的な衝撃や擦れによってめっき層が剥がれたり、薄くなったりすると、鉄素地が露出し、その部分から赤錆が発生します。輸送中や組立工程での接触傷も原因の一つです。
めっき厚の不足
めっき層が薄すぎると、酸素や水分の侵入を防げず、赤錆が発生しやすくなります。特に電気亜鉛めっきは、膜厚が薄い場合に防食寿命が短くなる傾向があります。
不適切な下地処理
めっき前の脱脂・酸洗処理が不十分であると、鉄表面に油分や酸化皮膜が残り、めっきの密着性が低下します。これにより局部的なめっき不良が生じ、そこから赤錆が発生します。
使用環境による劣化
屋外環境や海岸地域など、湿気や塩分が多い場所ではめっきが徐々に劣化します。特にクロメート処理をしていない亜鉛めっきは、赤錆が生じやすい傾向があります。
白錆・赤錆の防止対策
防錆処理を強化する
亜鉛めっきの後処理として行われる「クロメート処理」や「ジンクニッケルめっき」などの防錆処理を行うことで、白錆や赤錆の発生を大幅に抑制できます。クロメート処理は、めっき表面に酸化皮膜を形成し、腐食を抑える効果があります。特に三価クロメート処理やジオメット処理は、環境対応型として広く採用されています。
保管時の湿気対策
製品を保管する際は、乾燥した場所を選び、直射日光や結露を避けることが重要です。通気性の良い梱包材を使用し、乾燥剤を併用することで湿度上昇を防げます。ビニール袋など密閉性の高い資材を使う場合は、必ず防錆紙を挟み込むようにしましょう。
取り扱い時の注意
めっき部品を素手で触れると、皮脂や汗に含まれる塩分・有機酸が原因で腐食が起こることがあります。作業時には必ず手袋を着用し、めっき面を直接触れないようにするのが基本です。
めっき後の完全乾燥
めっき後の水洗処理を終えたら、できるだけ早く完全乾燥させることが重要です。水分が残ると、局部電池反応により白錆が急速に進行します。特に袋詰め前の工程では、温風乾燥や真空乾燥などを用いると効果的です。
環境条件に合わせためっき選定
屋外使用や海岸地域など、腐食が進みやすい環境では、一般的な電気亜鉛めっきでは防食寿命が短くなります。その場合、「溶融亜鉛めっき」や「ジンクニッケル合金めっき」「クロムめっき」など、より耐食性の高い表面処理を選定することが望ましいです。
発生後の対処方法
白錆が発生した場合
白錆は初期段階であれば、柔らかい布やブラシで軽くこすり落とすことができます。表面の酸化亜鉛層を除去した後、再度防錆油を塗布することで進行を抑制できます。ただし、深い腐食が進行している場合は、再めっき処理が必要です。
赤錆が発生した場合
赤錆が見られる場合、すでに鉄素地が腐食しています。錆取り剤(リン酸系など)で除去した後、再めっきまたは防錆塗装を行う必要があります。早期に対処しないと、腐食が内部まで広がり、構造強度を損なうおそれがあります。
めっき品質とメンテナンスの重要性
めっきによる防錆は「永続的」なものではなく、環境条件や保管状態によって寿命が大きく変わります。高品質なめっき処理と正しい取り扱いを組み合わせることで、製品寿命を大幅に延ばすことができます。
また、定期的な外観点検や軽度の防錆油再塗布を行うことで、白錆・赤錆の進行を未然に防ぐことが可能です。
まとめ
鉄のめっき後に発生する白錆と赤錆は、どちらも環境条件や取り扱い方法に大きく左右されます。
白錆は亜鉛層が腐食している段階、赤錆は鉄そのものが腐食している段階です。
防錆処理の強化、乾燥・保管管理、適切なめっき選定を徹底することで、錆の発生を最小限に抑えることができます。
いかがでしたでしょうか?
金属加工.comでは、他にも金属加工関連の情報を発信しております。他にも気になる記事がありましたら、是非ご覧ください。
金属加工.comのトップページはこちら↓

関連記事はこちら↓







