鉄の鍍金後に発生する水素脆化とは?~原因と防止方法~
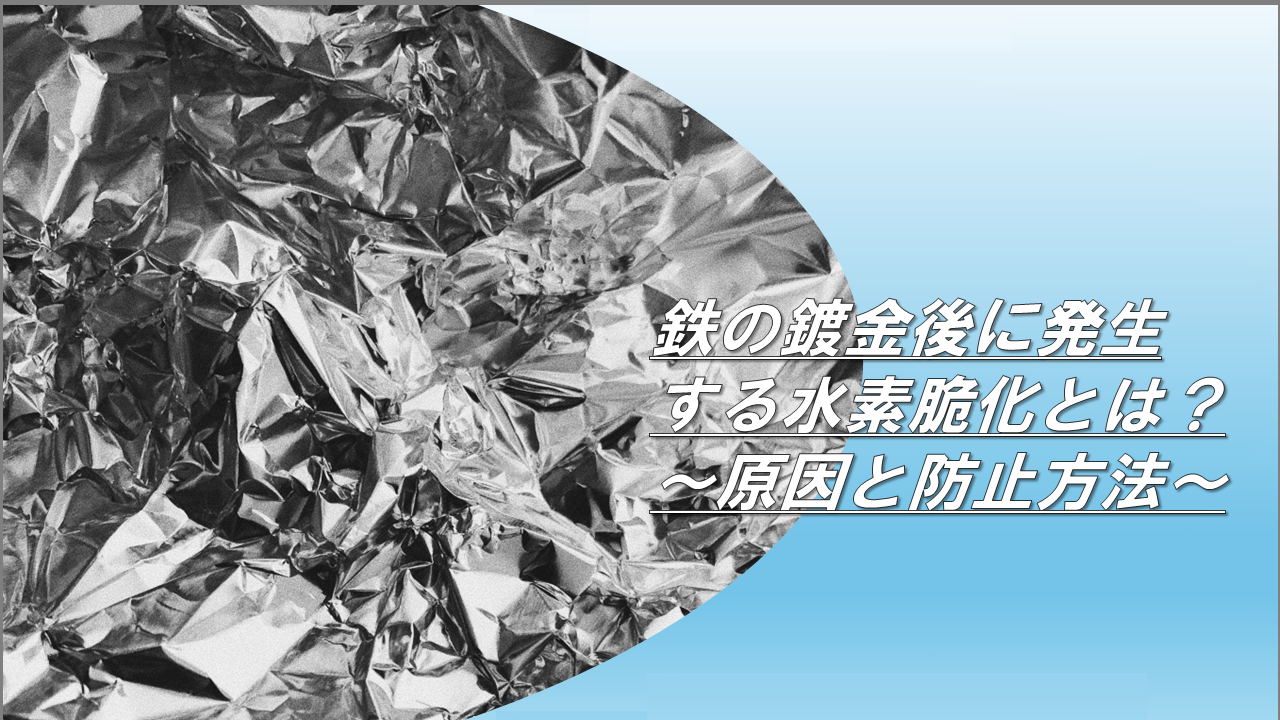
金属加工.comをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、山梨県・長野県にて切削加工やろう付けを行っている 北東技研工業株式会社 が運営しております。
金属加工に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
水素脆化とは何か
鉄や鋼材に「めっき」処理を施すと、表面が美しくなるだけでなく、耐食性も向上します。しかし、めっきの過程で注意しなければならない問題の一つに「水素脆化(すいそぜいか)」があります。水素脆化とは、金属内部に侵入した水素原子が原因で、金属がもろくなり、破断しやすくなる現象のことを指します。外観上は何も変わらなくても、内部にひずみや割れが発生してしまうため、非常に厄介な現象です。
特に、強度の高い高張力鋼やバネ鋼などは水素の影響を受けやすく、わずかな量の水素でも破壊に至ることがあります。めっき後のトラブルの中でも、最も深刻な問題の一つと言えるでしょう。
水素脆化が起こる仕組み
水素脆化は、主に「水素が鉄の内部に入り込み、金属結晶を弱める」ことによって発生します。鉄の表面で発生した水素原子が内部に侵入し、金属内部の欠陥や粒界に溜まることで、金属結合が弱まります。これが応力の集中を引き起こし、結果として微細な割れが発生しやすくなるのです。
水素の侵入経路
鉄への水素侵入は、めっき工程中に複数の経路で起こります。主な経路は以下の通りです。
- 酸洗いや脱脂処理で発生する水素ガスの吸収
- 電気めっき中に陰極反応として発生する水素の吸収
- 酸洗後に十分な乾燥や脱水がされていない場合の残留水素
特に電気めっきでは、金属表面で水素イオンが電子を受け取り水素原子や分子になる反応が起こります。この時、一部の水素が表面から抜け出さず、金属内部に吸収されてしまうのです。
めっきで水素脆化が問題となる理由
めっき工程では、鉄素材が電解液に浸されるため、必然的に水素が発生しやすい環境となります。特に亜鉛めっき、ニッケルめっき、クロムめっきなどの電気めっきでは、水素発生反応と金属析出反応が同時に起こっています。そのため、めっき後に水素が金属内部に残留しやすく、脆化の原因となるのです。
また、めっき前の下処理である酸洗いや電解脱脂の工程でも、酸性溶液が鉄と反応して水素を発生させるため、水素吸収のリスクが高まります。表面処理の品質がいくら高くても、この水素を取り除かない限り、内部応力によってクラックや破断が発生する危険性があります。
水素脆化が発生しやすい条件
水素脆化の発生には、いくつかの条件が関係します。特に以下の3つは重要な要因です。
材料の強度が高い場合
高強度鋼(引張強さが1000MPa以上)になるほど、水素脆化の感受性が高まります。これは、結晶構造内のひずみが大きく、水素が侵入しやすい欠陥が多く存在するためです。したがって、バネ鋼、ボルト、ナット、シャフトなどの高強度部品では特に注意が必要です。
応力がかかっている場合
水素脆化は、静的な引張応力や残留応力が存在する場合に顕著になります。応力が集中している箇所に水素が集まることで、マイクロクラック(微細な割れ)が発生し、最終的に破断につながります。
水素除去処理が不十分な場合
めっき後に適切な「ベーキング処理」(水素除去焼鈍)が行われないと、水素が金属中に残留します。特にめっき後24時間以内に処理を行わないと、脆化のリスクが大幅に上昇します。
水素脆化の主な症状と見分け方
水素脆化は、外観上は正常に見えることが多く、非常に見つけにくい特徴があります。代表的な症状は次の通りです。
- めっき後に時間が経ってから破断する「遅れ破壊」
- 曲げ試験や引張試験で突然破断する
- 表面に微細な割れが現れ、進行すると破断に至る
特に「遅れ破壊」は厄介で、めっき直後には異常がなくても、数時間から数日後に突然破壊が起こることがあります。そのため、検査では見逃されやすく、実際の使用環境下で事故につながることもあります。
水素脆化の防止方法
水素脆化を完全に防ぐことは難しいですが、発生リスクを大幅に低減することは可能です。ここでは、代表的な防止策を紹介します。
めっき前処理の最適化
酸洗いや脱脂の工程では、過度に強い酸を使用せず、水素発生を最小限に抑えることが重要です。酸洗時間を短縮したり、酸化皮膜を物理的に除去するなどの工夫も有効です。
めっき条件の改善
めっき電流密度を下げることで、水素の発生量を抑えることができます。また、添加剤の選定や攪拌条件の見直しも有効です。過度な電流や高温環境は水素の吸収を促進するため、工程管理が不可欠です。
ベーキング処理(水素除去焼鈍)
もっとも効果的な防止方法が「ベーキング処理」です。めっき後すぐに部品を加熱し、水素を拡散させて除去します。一般的には以下の条件が推奨されます。
- 温度:180~230℃
- 時間:2~4時間(厚みや材質により調整)
- 処理タイミング:めっき後1~2時間以内に実施
この処理により、金属内部に残留した水素が外部へ放出され、脆化を防止することができます。
高強度鋼への対応
高強度鋼部品を扱う場合は、めっき以外の防錆処理を検討するのも一つの手です。たとえば、化成処理や無電解めっき(例:無電解ニッケル)などは水素発生が少なく、水素脆化のリスクを抑えられます。
水素脆化を防ぐための設計上の注意点
製品設計の段階でも、水素脆化を防ぐ工夫が可能です。応力集中が起こりやすい形状を避けたり、適切な熱処理を組み合わせることで安全性を高められます。
- 角部や段差をできるだけ丸めて応力集中を緩和する
- めっき前後で過大な機械的応力を与えない
- 使用中の引張応力を最小限に抑える設計を心がける
また、部品を組み立てた後に熱処理を行うことで、残留応力と水素を同時に除去できる場合もあります。
水素脆化の評価・検査方法
水素脆化の確認には、専用の試験が必要です。代表的な評価方法は以下の通りです。
- 遅れ破壊試験:一定の応力を加えて破断までの時間を測定
- 引張試験:めっき前後の機械的特性の比較
- 顕微鏡観察:破断面の脆性破壊痕を確認
また、非破壊検査として磁粉探傷や浸透探傷なども併用されます。これにより、表面や内部の微小なクラックを早期に発見することができます。
まとめ
鉄のめっきは、見た目の美しさや耐食性の向上に欠かせない表面処理ですが、その裏には「水素脆化」という重大なリスクが潜んでいます。
この現象は、目に見えない水素が金属内部に侵入することで、応力集中や遅れ破壊を引き起こす非常に厄介な問題です。
しかし、めっき工程の管理とベーキング処理を適切に行えば、リスクは大幅に低減できます。
水素脆化を防ぐためには、
- めっき前後の処理条件を厳密に管理する
- 高強度材では無電解めっきや化成処理を検討する
- 設計段階から応力集中を避ける
といった総合的な対策が必要です。
鉄製部品の信頼性を保つためには、「見た目の品質」だけでなく、「内部の安全性」にも十分な配慮を行うことが求められます。
いかがでしたでしょうか?
金属加工.comでは、他にも金属加工関連の情報を発信しております。他にも気になる記事がありましたら、是非ご覧ください。
金属加工.comのトップページはこちら↓

関連記事はこちら↓







