真鍮の熱処理方法と効果
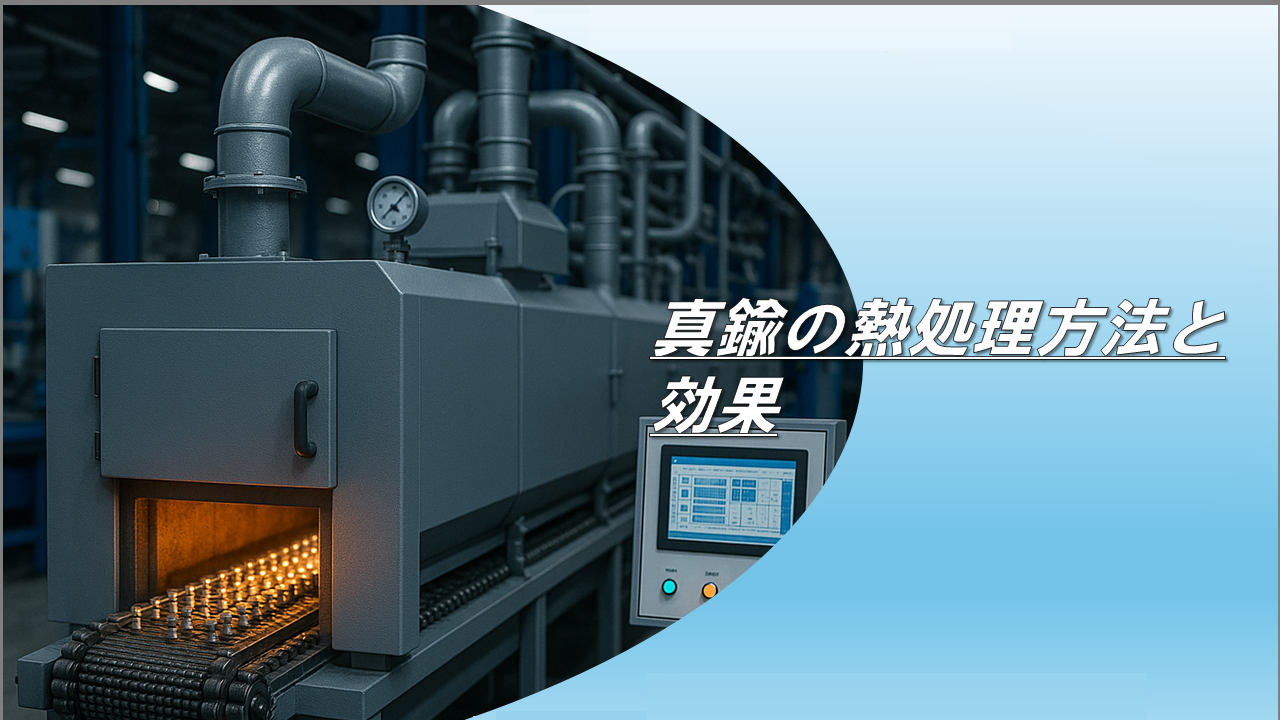
金属加工.comをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、山梨県・長野県にて切削加工やろう付けを行っている 北東技研工業株式会社 が運営しております。
金属加工に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
真鍮は銅と亜鉛を主成分とする合金であり、装飾品から機械部品まで幅広い分野で利用されています。その理由の一つは、比較的容易に加工ができ、かつ美しい金色の外観を持つことです。しかし、使用環境や加工条件によっては、硬さや延性、耐食性などの特性を調整する必要が出てきます。その際に重要な技術が「熱処理」です。真鍮の熱処理は、適切に行うことで組織や機械的性質をコントロールでき、用途に応じた性能を引き出すことが可能です。本記事では、真鍮の代表的な熱処理方法とその効果について詳しく解説していきます。
真鍮に熱処理が必要とされる理由
真鍮は銅合金の中でも加工性に優れた金属ですが、加工を重ねることで「加工硬化」と呼ばれる現象が起こります。これは、曲げや引張り、プレスなどの冷間加工によって金属の結晶格子に欠陥が増え、硬く脆くなる状態です。加工硬化が進むと割れやすくなり、成形性が著しく低下します。そのため、途中で熱処理を加え、内部応力を取り除いたり延性を回復させたりすることが必要です。さらに、熱処理は機械的性質だけでなく、耐食性や電気伝導率にも影響を与えるため、適切な条件で行うことで製品寿命や信頼性の向上につながります。
真鍮に用いられる主な熱処理の種類
真鍮に適用される熱処理は、主に「焼なまし」「応力除去焼なまし」「析出硬化(場合によっては時効硬化)」の3つが中心です。それぞれの特徴と目的について整理してみましょう。
焼なまし(Annealing)
焼なましは、真鍮を一定温度まで加熱し、その後ゆっくり冷却する処理です。冷間加工によって硬化した真鍮の組織を再結晶させ、延性を回復させる効果があります。焼なましを行う温度は通常300〜600℃程度で、真鍮の種類や目的によって調整されます。適切な焼なましを行うことで、次の加工がスムーズに行えるようになり、製品の割れや欠陥を防止できます。
応力除去焼なまし(Stress Relief Annealing)
真鍮部品は機械加工や冷間加工によって内部に残留応力を抱えることがあります。この残留応力は、時間の経過や使用環境で変形や割れを引き起こす要因となるため、製品の寸法安定性を求められる場合には除去が不可欠です。応力除去焼なましは200〜300℃程度の比較的低温で加熱し、徐冷することで残留応力を取り除きます。機械部品や精密部品の寸法安定性を確保するために広く利用されています。
析出硬化・時効硬化(Precipitation Hardening / Age Hardening)
一部の真鍮、特に特殊成分を含む合金では、熱処理によって析出物を形成させることで強度を向上させることが可能です。これを析出硬化または時効硬化と呼びます。真鍮は基本的には析出硬化型合金ではありませんが、アルミニウムやマンガンを含む特種黄銅では、この処理によって硬度や耐摩耗性が向上する場合があります。高強度が求められる用途や耐摩耗性が重視される部品では、有効な手段となります。
熱処理の具体的なプロセス
真鍮に対する熱処理は、温度管理と冷却速度が非常に重要です。ここでは代表的なプロセスを説明します。
焼なましの手順
- 真鍮を炉内で300〜600℃に加熱する。
- 一定時間保持し、結晶粒を再結晶させる。
- 空冷または徐冷する。
急冷すると割れや歪みの原因となるため、基本的にはゆっくりと冷やすのが一般的です。焼なまし後は柔らかくなり、次工程の曲げや絞り加工が容易になります。
応力除去焼なましの手順
- 真鍮を200〜300℃に加熱する。
- 数十分から数時間保持する。
- 炉冷または空冷で徐冷する。
この処理によって残留応力が取り除かれ、加工後の部品が長期にわたり安定した形状を保つことが可能になります。
特殊黄銅の時効処理
- 溶体化処理として高温で加熱し、急冷する。
- その後、比較的低温で時効処理を行い、析出物を形成させる。
ただし、この手法はすべての真鍮に適用できるわけではなく、特定の合金系に限定されます。
熱処理による効果
真鍮の熱処理はさまざまな効果をもたらします。代表的なものを以下に整理します。
加工性の改善
冷間加工で硬化した真鍮は、そのままではさらに加工を加えるのが困難です。焼なましを行うことで柔らかさを取り戻し、追加の曲げや成形を可能にします。これにより複雑な形状の部品を製作できるようになります。
寸法安定性の向上
応力除去焼なましによって残留応力を取り除くと、長期使用でも歪みや変形が起こりにくくなります。これは精密機械部品や計測器など、高精度が要求される分野で特に重要です。
強度と耐摩耗性の向上
特殊成分を含む真鍮においては、時効処理を施すことで析出硬化が起こり、硬度や耐摩耗性が向上します。これにより、摩擦や衝撃を受ける部品でも長寿命化が可能となります。
耐食性への影響
熱処理によって結晶構造が整うことで、腐食に対する抵抗性が改善する場合があります。ただし、条件を誤ると逆に亜鉛の偏析が生じ、脱亜鉛腐食が進行する危険性もあるため、適切な処理が求められます。
真鍮の種類と熱処理適性
真鍮には亜鉛含有量や添加元素によってさまざまな種類があり、熱処理の効果も異なります。
例えば、亜鉛含有量が30%以下のα相真鍮は延性が高く、焼なましによって加工性をさらに改善できます。一方、亜鉛含有量が40%以上になるとβ相が現れ、硬さは増すものの延性が低下するため、熱処理条件の調整が難しくなります。また、アルミニウムやマンガンを添加した特殊黄銅では、時効硬化による強度向上が期待できます。
実際の応用例
真鍮の熱処理は、さまざまな産業分野で活用されています。
- 電気部品:焼なましを施すことで加工性を確保し、端子やコネクタに成形。
- 精密機械:応力除去焼なましにより寸法安定性を確保し、歯車や計測機器に利用。
- 装飾品:熱処理によって美しい表面を維持しながら加工。
- バルブや配管部品:析出硬化処理によって耐摩耗性を強化。
熱処理の注意点
真鍮の熱処理を行う際には、いくつかの注意点があります。
- 温度管理の精度:過加熱すると結晶粒が粗大化し、逆に強度や耐食性が低下する可能性があります。
- 冷却速度の制御:急冷は割れの原因となるため、基本的には徐冷が推奨されます。
- 大気との反応:高温加熱中に酸化や脱亜鉛が進む可能性があるため、保護雰囲気下で行うのが望ましい場合があります。
まとめ
真鍮の熱処理は、機械的性質や耐食性をコントロールするために欠かせない工程です。焼なましによる加工性改善、応力除去焼なましによる寸法安定性の確保、さらに特殊合金での時効硬化による強度向上など、それぞれの方法に応じて多様な効果を得ることができます。適切な熱処理を行うことで、真鍮は装飾品から精密部品まで幅広い用途でその特性を最大限に発揮できます。熱処理条件の選定は、製品の性能と寿命を左右する重要な要素であり、真鍮を扱う上で避けて通れない知識といえるでしょう。
いかがでしたでしょうか?
金属加工.comでは、他にも金属加工関連の情報を発信しております。他にも気になる記事がありましたら、是非ご覧ください。
金属加工.comのトップページはこちら↓

関連記事はこちら↓







