真鍮と青銅の熱伝導率比較
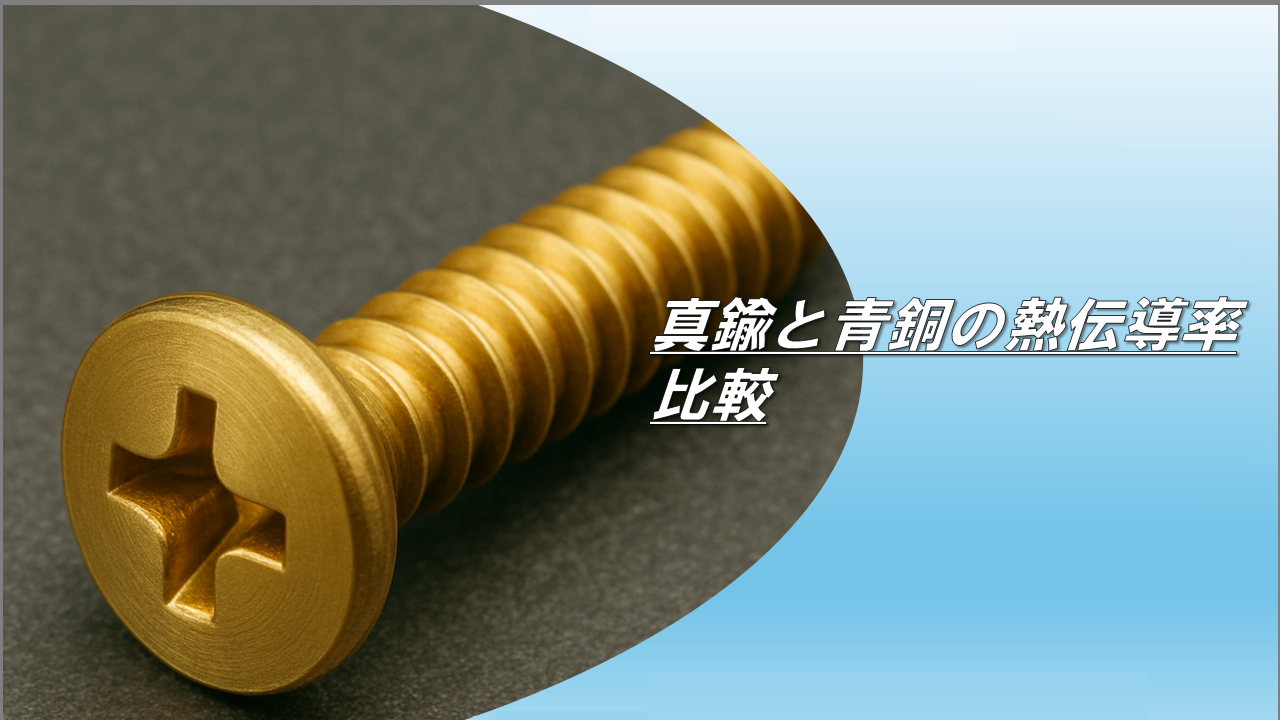
金属加工.comをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、山梨県・長野県にて切削加工やろう付けを行っている 北東技研工業株式会社 が運営しております。
金属加工に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
金属材料の特性を考える際に「熱伝導率」は欠かせない指標の一つです。熱伝導率が高ければ熱を素早く伝えることができ、逆に低ければ熱が伝わりにくい性質を持ちます。身近な例では、鍋やフライパンなどの調理器具には熱伝導率の高いアルミニウムや銅が多く使われています。一方で、熱伝導率が低い材料は断熱性や熱の保持が求められる用途で活躍します。
本記事では、銅合金の代表である「真鍮」と「青銅」に注目し、それぞれの熱伝導率を比較しながら、特徴や用途への影響について解説していきます。
真鍮とはどのような金属か
真鍮(しんちゅう)は、銅と亜鉛を主成分とする合金です。銅に対して亜鉛の割合を変えることで、色調や機械的性質が変化します。一般的には亜鉛含有量が20〜40%程度のものが多く使われています。
真鍮の特徴は、加工のしやすさと美しい黄金色の外観です。切削加工性が良く、装飾品や楽器、建材、精密部品など幅広い分野で利用されています。また、銅の持つ耐食性もある程度引き継いでいるため、湿気や水分に触れる環境でも比較的安定した性能を発揮します。
熱伝導率の観点では、銅に比べると亜鉛の影響で低下しますが、それでも一般的な鉄鋼材料よりは高い値を示します。
青銅とはどのような金属か
青銅(せいどう)は、銅に錫(すず)を加えた合金を指します。歴史的に最も古い合金の一つであり、紀元前から武器や工具、芸術品に広く使われてきました。青銅器という言葉があるように、人類史の技術発展において重要な役割を果たしています。
錫の含有量は通常5〜20%程度であり、これにより硬さや耐摩耗性が大きく向上します。さらに耐食性も高く、海水環境でも比較的安定して使用できることから、船舶用部品や軸受、歯車、彫像などに活用されています。
ただし、錫は銅に比べて熱伝導率が低いため、青銅全体としても熱を伝える能力はあまり高くありません。
真鍮と青銅の熱伝導率の数値比較
熱伝導率は一般的に「W/m・K」という単位で表されます。これは1メートルの厚みを持つ材料を1ケルビン温度差で熱がどれだけ流れるかを示す値です。
参考値として、代表的な金属の熱伝導率を挙げると以下のようになります。
- 純銅:約400 W/m・K
- アルミニウム:約237 W/m・K
- 鉄:約80 W/m・K
- ステンレス鋼:約15 W/m・K
これに対して、真鍮と青銅は次のような値を示します。
- 真鍮:約100〜150 W/m・K
- 青銅:約40〜70 W/m・K
この比較から分かるように、真鍮は青銅に比べておよそ2倍前後の熱伝導率を持っています。つまり、真鍮の方が熱を伝えやすく、熱交換や放熱の用途に適しているといえます。
熱伝導率の差が用途に与える影響
真鍮と青銅の熱伝導率の違いは、それぞれの用途に大きな影響を与えています。
真鍮の用途と熱伝導性の関係
真鍮は比較的熱伝導率が高いため、熱の伝達が求められる部品や製品に適しています。例えば、ヒートシンクや熱交換器の一部には真鍮が使われることがあります。また、楽器においても熱伝導率が影響し、吹奏楽器の表面温度の均一化や音響特性に寄与します。
さらに加工性の高さも相まって、真鍮は水道金具、精密機械部品、装飾品など幅広い分野に利用されています。これらの分野では、熱伝導率の高さは二次的な利点として活かされています。
青銅の用途と熱伝導性の関係
青銅は熱伝導率が低いため、熱を急速に逃がしたくない用途に適しています。例えば、軸受や摺動部品では、摩擦熱が発生しても急激に熱が広がらず、局所的な潤滑作用や安定した作動を助けます。また、青銅の耐摩耗性や耐食性の高さも相まって、機械の信頼性を高めています。
さらに芸術品や彫像といった分野でも青銅は重宝されます。熱伝導率の低さは製造時の鋳造工程において冷却速度を緩やかにし、細部まで安定して成形するのに有利に働きます。
合金組成による熱伝導率の変化
真鍮や青銅はそれぞれの主成分である銅に、亜鉛や錫を添加した合金です。そのため、添加量によって熱伝導率は大きく変化します。
- 真鍮では、亜鉛の割合が増えるほど熱伝導率は低下します。亜鉛は銅に比べて熱伝導率が低いため、合金全体の性能を下げてしまうからです。
- 青銅でも同様に、錫の割合が多いほど熱伝導率は低下します。特に錫含有量が20%に近い青銅はかなり低い熱伝導率を示します。
つまり、真鍮と青銅の熱伝導率は「亜鉛や錫をどれだけ含むか」によって幅があり、用途に応じて調整されているといえます。
他の性質とのバランス
熱伝導率だけを見れば真鍮の方が優れていますが、実際の材料選定では他の性質も重要です。例えば、機械的強度、耐摩耗性、耐食性、加工性、コストなどです。
- 真鍮は加工性に優れ、見た目も美しいため、建材や装飾品でよく使われます。
- 青銅は耐摩耗性や耐食性が高いため、機械部品や海洋環境での使用に向いています。
したがって、熱伝導率の違いは材料選定の一要素であり、用途に応じたバランスが求められます。
まとめ
真鍮と青銅はどちらも銅を主成分とする合金ですが、熱伝導率には大きな差があります。真鍮はおよそ100〜150 W/m・Kと比較的高い値を示し、青銅は40〜70 W/m・K程度と低めです。この差は、亜鉛や錫といった添加元素の性質によるものです。
真鍮は熱を伝えやすいため熱交換や装飾用途に適し、青銅は熱を伝えにくい特性を生かして軸受や耐摩耗部品、彫像などに活用されています。
つまり、両者の熱伝導率の違いは単なる数値比較にとどまらず、それぞれの適材適所を決定づける重要な要素であるといえます。
いかがでしたでしょうか?
金属加工.comでは、他にも金属加工関連の情報を発信しております。他にも気になる記事がありましたら、是非ご覧ください。
金属加工.comのトップページはこちら↓

関連記事はこちら↓







