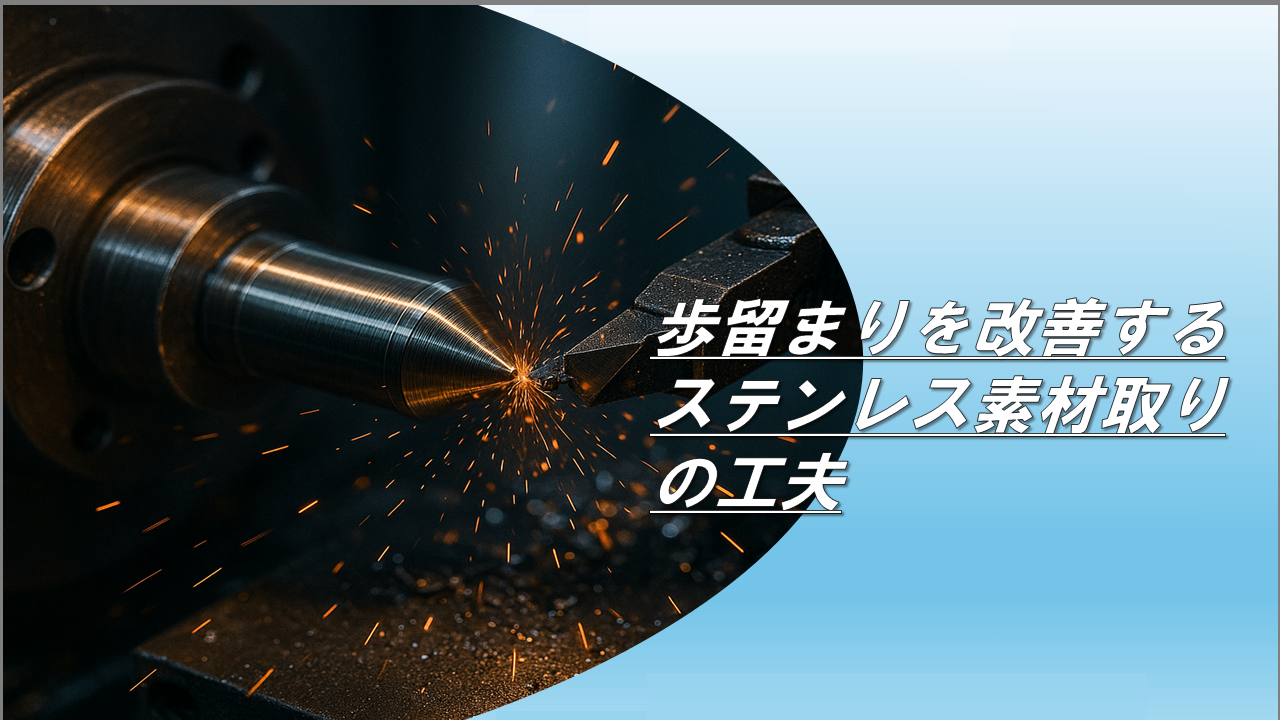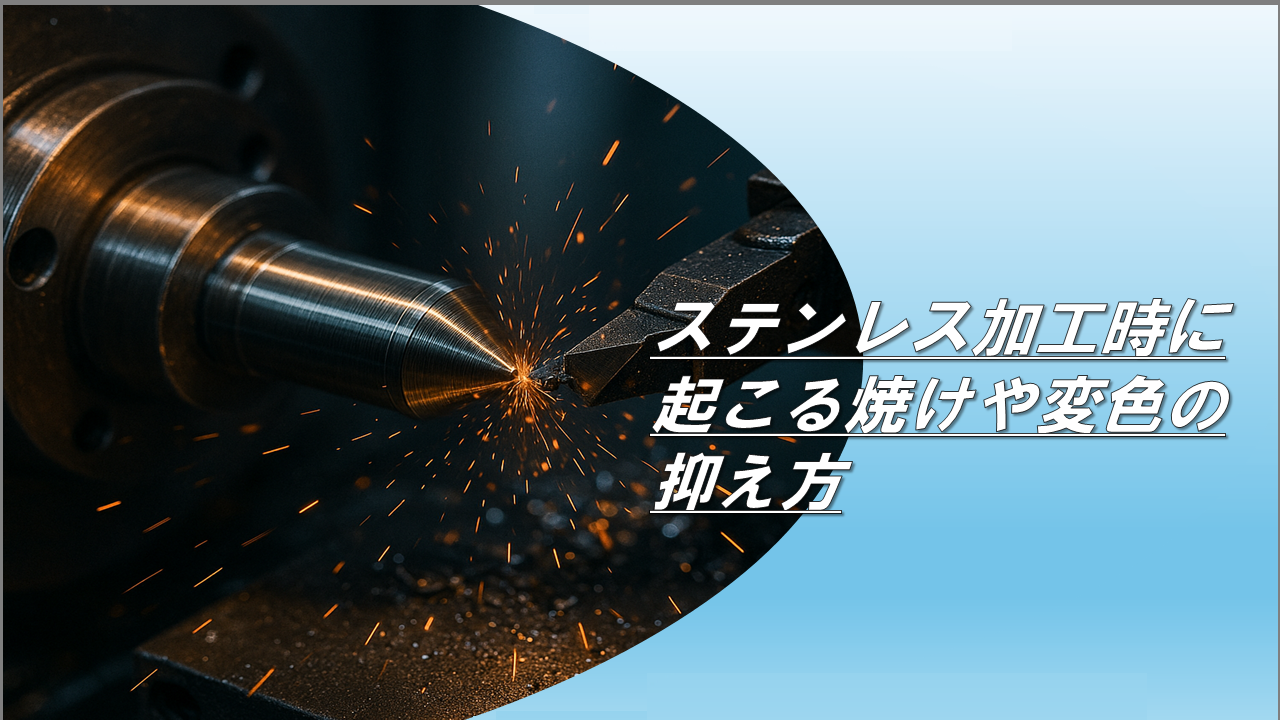ドライ切削でステンレスを加工するのは可能か?

金属加工.comをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、山梨県・長野県にて切削加工やろう付けを行っている 北東技研工業株式会社 が運営しております。
金属加工に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
なぜ「ドライ切削」が注目されるのか?
製造現場では近年、環境負荷低減とコスト削減の観点から「ドライ切削(乾式切削)」が注目されています。特に、切削油の使用量を減らすことで、廃油処理コストや人体への悪影響を抑え、持続可能な生産体制の構築が可能になるためです。
しかし、被削材が「ステンレス鋼」である場合、その適用は容易ではありません。ステンレスは難削材の代表格であり、熱伝導率が低く、加工硬化を起こしやすいため、切削熱が工具に集中しやすいという特性があります。本稿では、ステンレスにおけるドライ切削の可否と現場での実用性について詳しく考察していきます。
ステンレスの切削特性と難しさ
ステンレス鋼には代表的な種類として以下のようなものがあります。
| 材質記号 | 種類 | 特徴 |
|---|---|---|
| SUS304 | オーステナイト系 | 非磁性、高耐食性、加工硬化しやすい |
| SUS316 | オーステナイト系 | Mo添加で耐食性向上、加工硬化顕著 |
| SUS430 | フェライト系 | 磁性あり、硬さ中程度、熱伝導率は高め |
| SUS420J2 | マルテンサイト系 | 焼入れ可能で硬い、切削性は悪い |
これらのステンレスは共通して以下のような問題を切削時に引き起こします。
- 切削熱が工具に集中する(熱伝導率が低いため)
- 加工硬化によって切削抵抗が上昇
- 刃先への溶着やビビリが起こりやすい
- 工具摩耗が早く進行する
これらの特徴から、冷却効果や潤滑効果を持つ「クーラント」の使用が一般的に推奨されてきました。
ドライ切削の基本概念と利点
ドライ切削とは、一切の切削油やクーラントを使用せずに行う加工方法です。代表的なメリットは以下の通りです。
- 環境負荷の軽減(廃油・排水ゼロ)
- 切削油コストの削減
- 作業環境の改善(ミスト・臭いの低減)
- 工作機械のクリーン化(クーラントによる腐食や汚染がない)
一方、切削熱の管理が難しくなるため、被削材や工具への負担が増大し、摩耗や寸法精度に悪影響を及ぼすリスクも高くなります。
ステンレスに対するドライ切削の可能性
一般的には非推奨
ステンレスに対してドライ切削は、一般的には推奨されません。理由は以下のとおりです:
- 切削熱が高温になりやすく、工具の寿命を著しく短縮する
- 加工硬化が促進され、次工程に悪影響
- チップ溶着・バリの発生が顕著になる
- 加工面の品質(粗さ、寸法精度)が不安定になる
これらの問題から、特にオーステナイト系(SUS304/SUS316など)のステンレスでは、ドライ切削は避けるべきとされてきました。
近年の進展:ドライ切削の可能性について
ただし、特定条件下ではドライ切削も実用出来る可能性があります。
①耐熱性に優れたコーティング工具の使用
近年では、AlTiN(アルミチタン窒化物)やTiAlNなどの高硬度・高耐熱コーティング工具が普及しており、空冷でも工具温度をある程度まで維持することができます。
②高剛性・高精度マシニングセンタ
振動やビビリの抑制に優れた機械構造とスピンドル剛性がある加工機であれば、熱変形や加工誤差の発生を抑えられます。
③最適な切削条件の設定
例えば以下のような条件調整が必要です。
- 低送り、低切込み(断熱層形成を抑制)
- 高速回転(熱の排出促進)
- ドライ専用のチップブレーカ付きインサート使用
④送風(エアブロー)によるチップ排出
クーラントの代わりに高圧エアブローで切りくずを排出する方法もあり、これによって切削点の温度管理やチップ巻き付き抑制が可能になります。
適用できる場面・避けるべき場面
ドライ切削が可能な可能性があるケース
- フェライト系ステンレス(SUS430など):熱伝導率が高く、熱管理がしやすい
- 精密部品ではなく、粗加工や下地切削など、表面粗さや精度を厳密に求めない工程
- 加工機・工具・条件が最適化されている自動ライン
ドライ切削を避けるべきケース
- SUS304/SUS316などオーステナイト系で高精度が求められる場合
- 焼入れや加工硬化が進んだ材料
- 面粗度や工具寿命が重要な仕上げ加工
まとめ
結論として、ステンレスのドライ切削は「一部の素材・工程・条件」において実現可能ですが、一般的には推奨される加工法ではありません。
環境配慮やコスト削減の要請が高まる中、切削技術と工具材料の進化によって、限定的な範囲でドライ切削が選択肢となる時代になりつつあります。しかしながら、その実施には「工具材質」「機械剛性」「条件設定」などの高度な最適化が前提です。
現場での採用にあたっては、十分なテストと評価を行い、品質・寿命・安全性のバランスを確認したうえで段階的に導入することが推奨されます。
いかがでしたでしょうか?
金属加工.comでは、他にも金属加工関連の情報を発信しております。他にも気になる記事がありましたら、是非ご覧ください。
金属加工.comのトップページはこちら↓

関連記事はこちら↓