ステンレス溶接で発生する変色の防止法
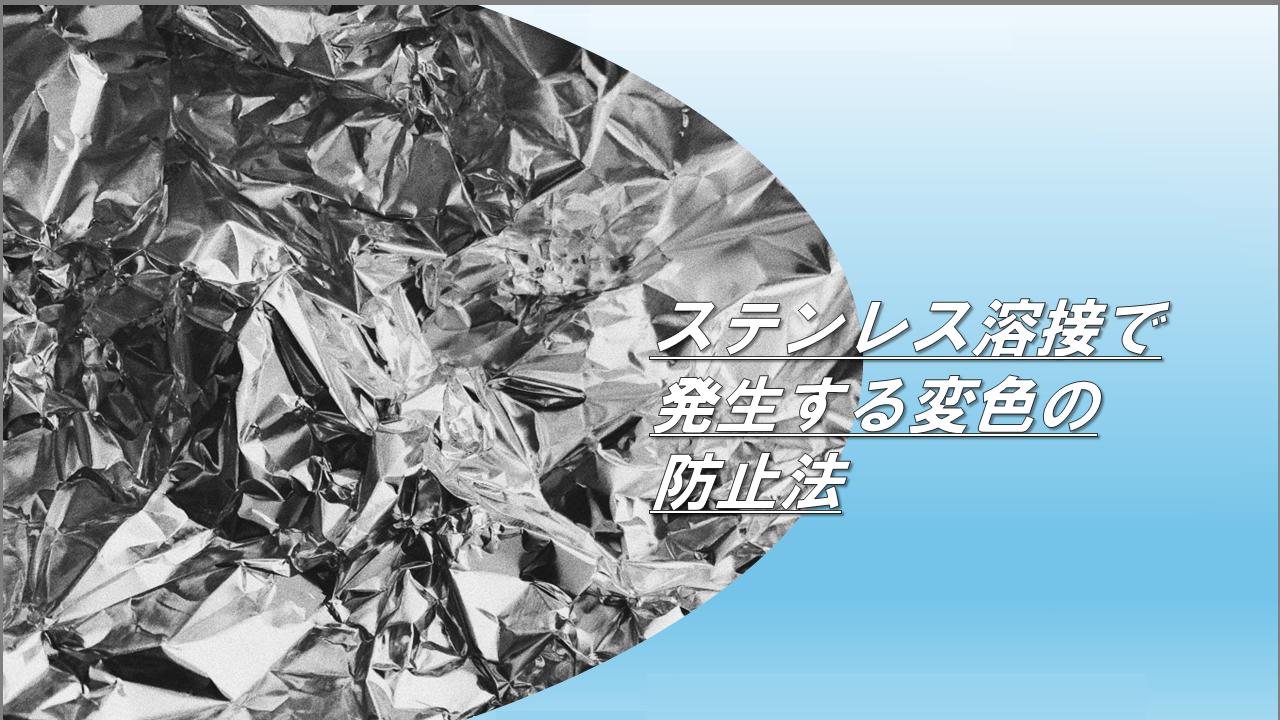
金属加工.comをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、山梨県・長野県にて切削加工やろう付けを行っている 北東技研工業株式会社 が運営しております。
金属加工に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
ステンレス鋼は、美しい光沢と優れた耐食性を持つことから、建築、食品機械、化学装置、医療機器など幅広い分野で使用されています。しかし、溶接を行う際に「変色」が生じることが多く、外観の低下や腐食抵抗の劣化を招く要因となります。本記事では、ステンレス溶接で発生する変色の原因と、防止・除去の方法について詳しく解説します。
ステンレス溶接における変色とは
ステンレス鋼をTIG溶接やレーザー溶接などで接合すると、溶接ビードやその周辺が「青色」「茶色」「黒色」に変化することがあります。これは、加熱によってステンレス表面に生成される**酸化皮膜(酸化クロム層)**が原因です。酸化皮膜の厚さによって見える色が異なり、温度が高いほど皮膜は厚く、色も濃くなります。
たとえば、
- 約200〜300℃では薄い金色や青色
- 約400〜600℃では濃い青紫色
- 600℃以上では黒色
といった変色が見られます。
この変色自体は、見た目の問題だけでなく、表面のクロム酸化物層のバランスが崩れることで耐食性が低下する点が問題です。特に酸化膜の下では「クロム欠乏層」が発生しやすく、局部腐食の起点になることがあります。
変色が発生する主な原因
酸素との接触
ステンレス溶接中に空気中の酸素と接触すると、溶融池およびその周辺が高温のまま酸化反応を起こします。アーク溶接ではアークの熱で金属温度が1000℃を超えるため、酸素が容易に酸化膜を形成します。
シールドガスの不十分な保護
TIG溶接などで使用するアルゴンなどのシールドガスが、溶融金属を十分に覆っていない場合、酸化が進み変色を引き起こします。ガス流量が少ない、トーチ角度が悪い、風の影響を受ける、あるいはノズル内の汚れなども原因になります。
裏面酸化(ルート部の酸化)
パイプや板の突き合わせ溶接では、裏面が空気に触れて酸化することがあります。これを「裏焼け」または「シュガー(糖状酸化)」と呼び、黒くザラザラした酸化物が発生します。裏焼けは見た目だけでなく、腐食の進行を早める危険な現象です。
加熱温度と冷却速度
溶接時の入熱が大きい場合や、冷却が遅い場合にも酸化反応が進行します。特に厚板や高電流溶接では、溶接熱が広い範囲に伝わり、熱影響部(HAZ)が変色しやすくなります。
変色を防止するための基本対策
シールドガスを適正化する
アルゴンガスを主に使用するTIG溶接では、適正な流量とガスカバー範囲の確保が重要です。ガス流量は通常10〜15 L/minが目安ですが、板厚や開先形状によって調整が必要です。流量が多すぎると乱流が発生し、逆に空気を巻き込みやすくなるため注意が必要です。
また、トーチの角度は母材に対して約70〜80°が理想的で、過度に寝かせるとガス保護範囲が狭くなります。
バックシールド(裏面保護)を行う
パイプ溶接や薄板の突き合わせ溶接では、裏面にもアルゴンガスを流して空気遮断を行う「バックシールド」が有効です。ガスの流量は3〜5 L/min程度が目安で、流しすぎると乱流が起きて逆効果となるためバランスが重要です。
また、専用の「パージダム」や「裏波パージフィルム」を使用することで、効率よく酸化を防止できます。
適切な入熱管理を行う
入熱量が過大になると、酸化だけでなく粒界の鋭敏化やひずみの原因にもなります。溶接条件を見直し、アーク電流・電圧・溶接速度を最適化することが大切です。
例えば、TIG溶接であれば電流をやや抑え、溶接速度を一定に保つことで過剰な加熱を防止できます。短時間で完了するパルスTIG溶接を用いるのも有効な方法です。
風や通気の影響を避ける
屋外や換気の強い環境では、アルゴンガスが吹き飛ばされやすく、変色が発生します。風防シートを設けたり、溶接中は換気方向を調整するなどの配慮が必要です。
溶接後すぐに冷却する
高温状態が続くと酸化膜の成長が進みます。溶接後は速やかに自然冷却させるか、軽く空冷することで変色を抑制できます。ただし急冷しすぎると割れのリスクがあるため、材質や板厚に応じて適度な冷却を行います。
溶接後に変色してしまった場合の対処法
酸洗による除去
変色が発生した場合、最も一般的な除去方法が「酸洗い」です。酸洗液には硝酸とフッ酸の混合液が使用され、酸化膜を溶解して表面を元の金属光沢に戻します。市販の「酸洗ペースト」を使用すれば、部分的な補修も可能です。
ただし、酸洗作業には換気と防護が必須であり、作業後には水洗と中和処理を徹底する必要があります。
機械的研磨
軽い変色であれば、ステンレス専用の不織布研磨材やバフを用いて除去できます。ただし、研磨しすぎると表面が粗くなり、逆に腐食しやすくなるため注意が必要です。研磨後は脱脂・清掃を行い、再酸化を防止します。
電解研磨
より美しい仕上げを求める場合は、電解研磨によって変色と表面の酸化膜を同時に除去する方法もあります。電解研磨は表面を均一に溶解し、光沢を取り戻すとともに耐食性を高めます。食品機械や医療機器分野では特に重視される工程です。
材質による変色のしやすさの違い
ステンレス鋼にはオーステナイト系、フェライト系、マルテンサイト系などの種類がありますが、変色の発生傾向も異なります。
- オーステナイト系(SUS304、SUS316など):最も一般的で変色しやすい。耐食性は高いが熱伝導率が低いため、局部加熱により酸化が進行しやすい。
- フェライト系(SUS430など):熱伝導率が高く、酸化は比較的穏やか。ただし高温強度が低いため、溶接後のひずみや割れに注意。
- マルテンサイト系(SUS410など):焼入れ性があり、溶接時に硬化・割れを起こしやすい。変色もやや顕著。
材質に応じて溶接条件やシールドガスの流量を調整することが、変色防止のポイントです。
現場で実践できる変色防止のチェックポイント
- アルゴンガスの流量を定期的に確認する
ガスボンベの残圧が下がると流量が安定しなくなります。流量計や圧力計を確認し、安定した供給を保つことが重要です。 - ノズルやトーチキャップの清掃を行う
スパッタやホコリが付着していると、ガス流が乱れて保護範囲が狭まります。 - 裏面ガスが均一に行き渡っているか確認する
パイプの端部をテープでしっかり密閉し、パージ中にガス漏れがないかチェックします。 - 溶接中の風向きを意識する
作業環境の風や吸排気装置の影響を受けにくい位置で溶接を行います。 - 溶接後の処理を怠らない
小さな変色でも、時間経過で腐食が進行することがあります。外観重視の部品では、必ず酸洗いやパッシベーション処理を行いましょう。
まとめ
ステンレス溶接における変色は、見た目の問題だけでなく、耐食性や製品寿命に直結する重要な要素です。その発生原因の多くは、酸素との接触や不十分なガス保護にあります。
適切なシールドガスの管理、入熱の制御、裏面のパージ処理を徹底することで、変色は大幅に防ぐことが可能です。
もし変色が発生してしまった場合でも、酸洗いや電解研磨などの適切な後処理を行えば、性能を回復させることができます。美観と機能を両立させるためには、溶接前の準備・溶接中の管理・溶接後の仕上げという「三段階の品質管理」が欠かせません。
ステンレス製品の品質を長期間維持するためには、単なる見た目の問題ではなく、「酸化=劣化のサイン」であることを理解し、日常的に変色防止の意識を持って溶接に取り組むことが大切です。
いかがでしたでしょうか?
金属加工.comでは、他にも金属加工関連の情報を発信しております。他にも気になる記事がありましたら、是非ご覧ください。
金属加工.comのトップページはこちら↓

関連記事はこちら↓







