ステンレスの磁性と非磁性材料の違い
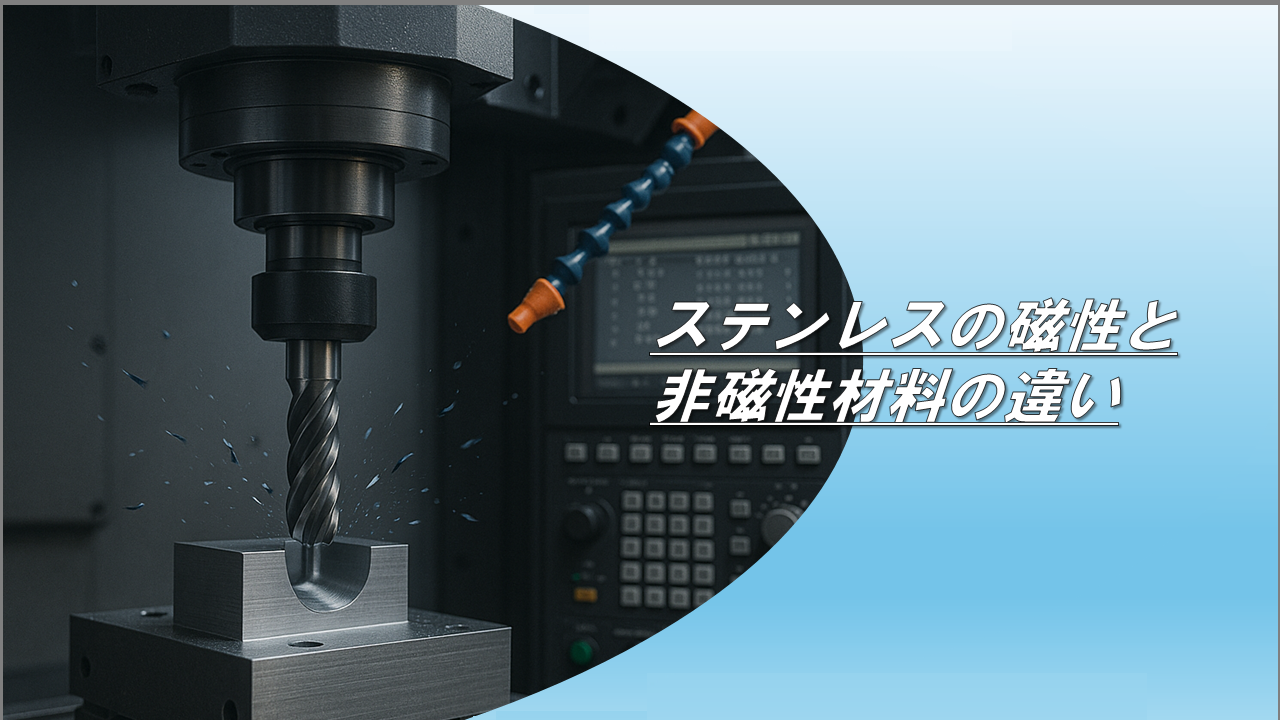
金属加工.comをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、山梨県・長野県にて切削加工やろう付けを行っている 北東技研工業株式会社 が運営しております。
金属加工に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
ステンレス鋼は、私たちの身の回りに広く使われている金属材料です。キッチン用品や医療機器、建築資材、自動車部品に至るまで、多岐にわたる分野で利用されています。その特徴といえば「錆びにくさ」が最もよく知られていますが、実はステンレスには「磁性を持つもの」と「磁性を持たないもの」が存在することはあまり知られていません。磁石につくかどうかで性質が分かれるこの違いは、日常の利用だけでなく、産業上の用途選定にも大きな影響を与えています。ここでは、ステンレス鋼の磁性の有無について、その仕組みや分類、特徴、さらに実用上の違いについてわかりやすく解説していきます。
ステンレスの基本構造と磁性の関係
ステンレスが磁石につくかどうかは、主に「結晶構造」によって決まります。鉄を主成分とする金属材料の磁性は、原子の持つ電子スピンの配列によって生じます。電子スピンが同じ方向にそろいやすい結晶構造を持つ場合は磁性が強くなり、逆にそろいにくい構造では磁性が弱まります。
ステンレス鋼は、添加されるクロムやニッケルの量によって結晶構造が変化します。代表的な結晶構造は以下の通りです。
- フェライト系ステンレス:体心立方構造(BCC)を持ち、強い磁性を示す。
- オーステナイト系ステンレス:面心立方構造(FCC)を持ち、通常は非磁性。
- マルテンサイト系ステンレス:体心立方構造の一種で、硬化処理により磁性を示す。
このように、ステンレスの磁性の有無は「どの系統のステンレスか」によって大きく左右されます。
磁性を持つステンレス鋼の特徴
磁石につくステンレスは主にフェライト系とマルテンサイト系です。
フェライト系ステンレス
フェライト系はクロムを主成分とし、ニッケルをほとんど含まないステンレスです。磁性が強く、比較的安価であるため、家電製品や厨房機器の裏材、自動車の排気系部品などに使われます。
- 代表的な鋼種:SUS430
- 特徴:耐食性は中程度、成形性はやや劣る、磁性が強い
マルテンサイト系ステンレス
マルテンサイト系はクロムを12~18%程度含み、熱処理によって硬化できるのが大きな特徴です。磁性を示すだけでなく、高い強度や耐摩耗性を持つため、ナイフや刃物、タービンブレードなどに利用されます。
- 代表的な鋼種:SUS410、SUS420
- 特徴:硬度が高く加工性はやや低い、磁性を持つ、耐食性は限定的
このように、磁性を持つステンレスは「構造部材」「刃物」「強度を必要とする部品」などに用いられることが多いです。
非磁性ステンレス鋼の特徴
磁石につかないステンレスの代表はオーステナイト系です。
オーステナイト系ステンレス
オーステナイト系はクロムに加えてニッケルを多く含んでおり、結晶構造が安定して非磁性を示します。最も広く使われるステンレスで、家庭用から産業用まで幅広い用途に用いられています。
- 代表的な鋼種:SUS304、SUS316
- 特徴:優れた耐食性、良好な加工性と溶接性、非磁性
特にSUS304は「18-8ステンレス」と呼ばれ、18%のクロムと8%のニッケルを含む合金です。錆びにくさと扱いやすさから、シンクや調理器具、建築物、医療機器などに広く使用されています。SUS316はモリブデンを加えることで耐孔食性を高め、海水や塩分環境に強い材料として利用されています。
加工によって磁性が変化する場合
一般的に「オーステナイト系=非磁性」と言われますが、完全に磁性がないわけではありません。強い塑性加工(曲げ、圧延、切削など)を受けると、一部がマルテンサイトに変態して弱い磁性を示す場合があります。
例えば、SUS304を深絞り加工したり冷間加工すると、磁石に少し反応することがあります。このため、磁性の有無だけで鋼種を判別することは難しいケースもあります。
磁性・非磁性ステンレスの用途の違い
磁性を持つかどうかは、用途の選定に直結します。
- 磁性ステンレスの用途
- 電磁調理器(IHクッキングヒーター)対応の鍋やフライパン
- 自動車部品(排気管、マフラー、ブレーキ部品)
- 構造材や機械部品
- 刃物、工具類
- 非磁性ステンレスの用途
- キッチンシンク、食器、調理器具
- 医療用機器(非磁性のためMRI室で使用可能)
- 建築物の外装や内装
- 化学プラント設備、船舶部材
特に医療や精密機器分野では「磁性があると使えない」ケースが多いため、非磁性ステンレスが必須となります。逆に、IH調理器具のように磁性がないと加熱できない場面ではフェライト系が選ばれます。
磁性の有無を見分ける方法
一般的に「磁石を近づけて反応を見る」方法が簡単です。ただし、前述のようにオーステナイト系でも加工によって弱磁性を帯びる場合があるため、正確な判別には成分分析や材質証明が必要です。工場や製造現場では、携帯型の材質分析装置(蛍光X線分析装置など)で判定することが一般的です。
磁性とコストの関係
ステンレス鋼のコストは、含まれる元素によって大きく変わります。
- 非磁性ステンレス(オーステナイト系)は、ニッケルを多く含むため価格が高め。
- 磁性ステンレス(フェライト系・マルテンサイト系)は、ニッケルをほとんど含まないため比較的安価。
そのため、コスト重視の分野ではフェライト系が選ばれる傾向があります。ただし、耐食性や加工性を求められる場合にはオーステナイト系が優先されます。
まとめ
ステンレス鋼には磁性を持つものと持たないものがあり、その違いは結晶構造と合金成分によって決まります。
- フェライト系、マルテンサイト系 → 磁性あり
- オーステナイト系 → 磁性なし(加工で弱磁性を帯びることもある)
磁性の有無は、用途に直結する重要な性質です。IH対応調理器具や自動車部品では磁性が必要とされ、医療機器や化学プラントでは非磁性が求められます。また、コストや加工性、耐食性といった観点でも、磁性・非磁性ステンレスの選び分けは非常に重要です。ステンレスの「磁石につくかどうか」という身近な性質は、実は材料科学や産業分野において大きな意味を持つ要素なのです。
いかがでしたでしょうか?
金属加工.comでは、他にも金属加工関連の情報を発信しております。他にも気になる記事がありましたら、是非ご覧ください。
金属加工.comのトップページはこちら↓

関連記事はこちら↓







