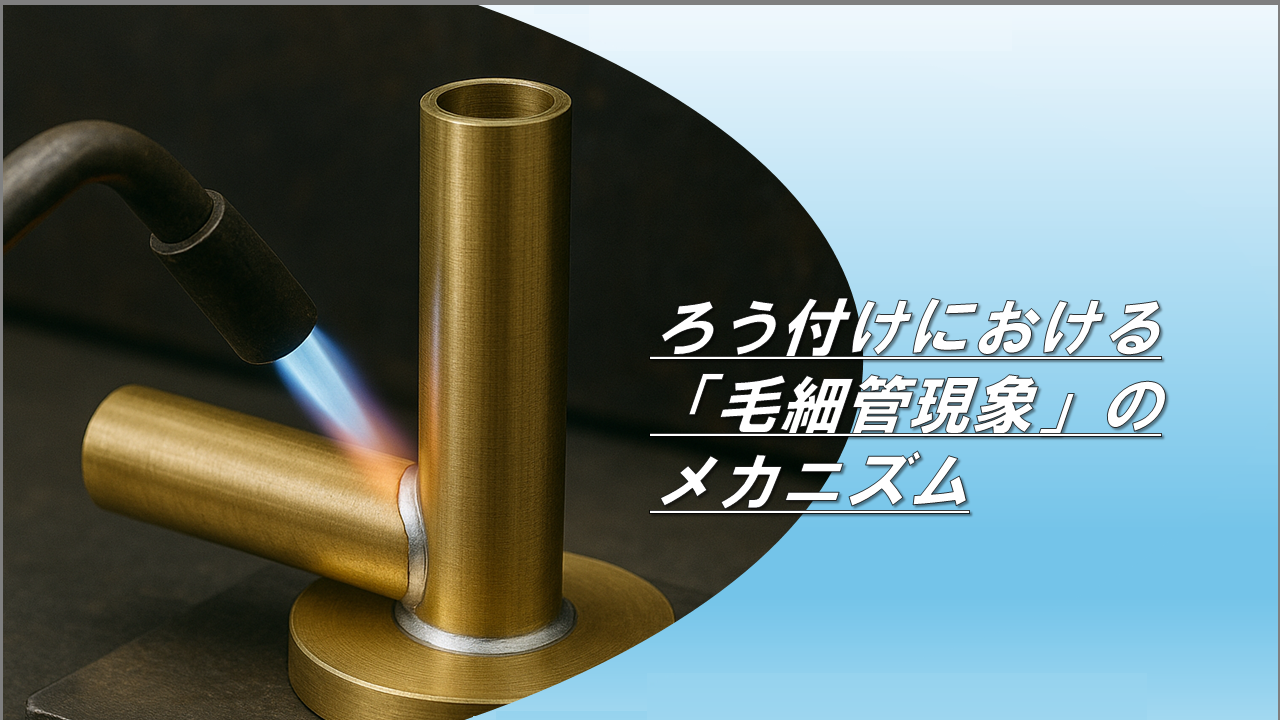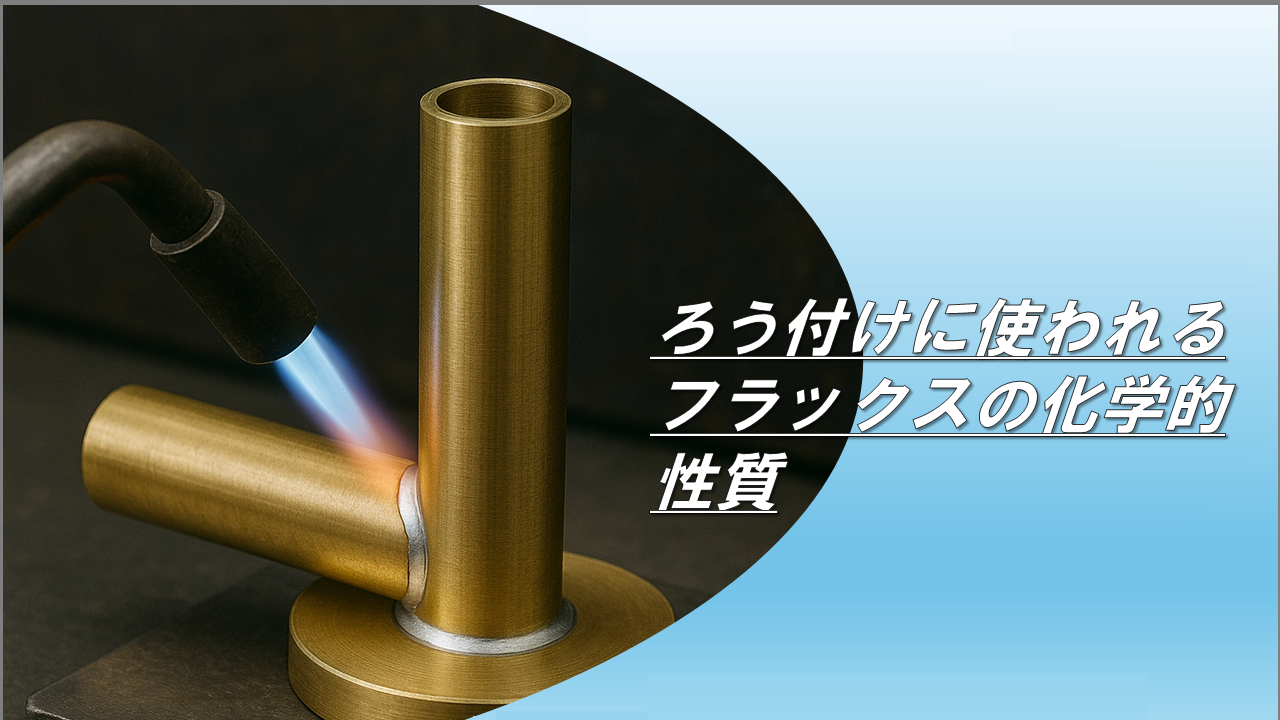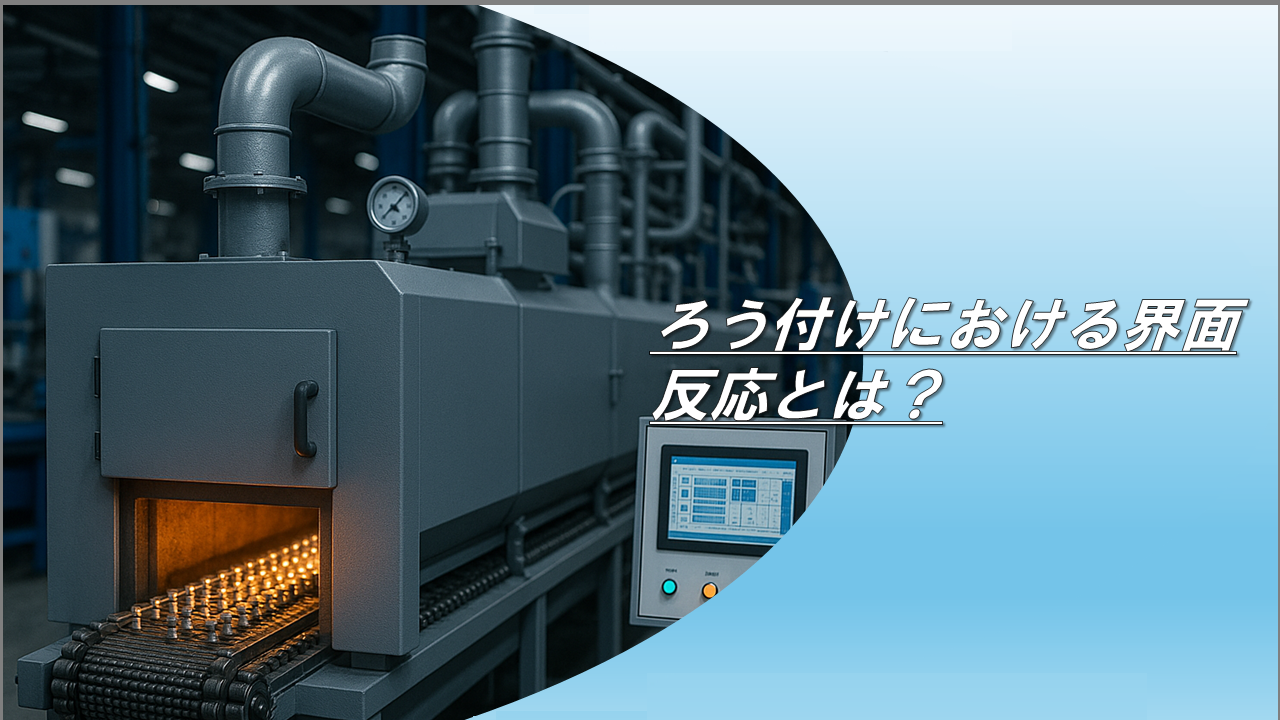ろう付け後の非破壊検査手法(X線・超音波など)

金属加工.comをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、山梨県・長野県にて切削加工やろう付けを行っている 北東技研工業株式会社 が運営しております。
金属加工に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
ろう付けは、異なる金属や同種金属を高温で接合する技術であり、自動車部品や航空機、精密機械など幅広い分野で活用されています。ろう付け接合では接合強度や耐久性が重要であり、作業後には品質を確認する工程が欠かせません。破壊検査では接合部を切断する必要があり、製品としての利用はできません。そのため、製品の品質を確保しつつ部品を破壊せずに確認できる「非破壊検査(Nondestructive Testing, NDT)」が広く用いられています。
本記事では、ろう付け後の非破壊検査手法について、代表的なX線検査や超音波検査を中心に、方法やメリット、注意点までわかりやすく解説します。
ろう付け後の非破壊検査の重要性
ろう付けは高温で母材とろう材を溶融し、毛細管現象によって接合する技術です。しかし、接合が均一に行われない場合や、内部に気泡や割れが発生することがあります。外観だけではこれらの欠陥を確認することは困難です。
非破壊検査を行うことで、内部の欠陥や接合不良を検出でき、製品の信頼性を確保できます。特に航空宇宙や自動車部品など、安全性が求められる分野では、非破壊検査が義務付けられる場合もあります。また、生産段階での品質管理にも不可欠で、欠陥の早期発見によってコスト削減にもつながります。
X線検査(ラジオグラフィ)
X線検査は、内部の密度差を利用して接合部の状態を可視化する方法です。ろう付け後の部品にX線を照射し、透過したX線の強度をフィルムやデジタルセンサーで記録します。密度の異なる部分や空洞は、画像上で濃淡として現れるため、内部の欠陥を確認できます。
X線検査の特徴
- 小さな気泡や内部空洞の検出に適している
- 接合不良やろう材の不均一も確認可能
- 金属の厚みや形状によって検査条件を調整する必要がある
X線検査の利点と注意点
利点として、非破壊で部品全体を観察できること、欠陥の位置や形状を把握しやすいことが挙げられます。一方で、高価な設備が必要であり、放射線を使用するため安全管理が必須です。また、厚い部材や複雑形状の部品は、画像の重なりやアーチファクトによって判別が難しくなることがあります。
超音波検査
超音波検査は、高周波の音波を利用して内部の欠陥を検出する方法です。検査対象に超音波を送信し、反射波や透過波を解析することで内部の構造を把握します。接合面や母材内部に空洞や割れがある場合、反射波の変化として検出されます。
超音波検査の種類
- パルス反射法: 超音波を送信し、欠陥で反射される波を観測する
- 透過法: 超音波を部材の一方から送り、反対側で受信する
- 位相ドップラー法: 表面の微小変形や振動を測定して内部状態を推定する
超音波検査の利点と注意点
超音波検査は、金属厚の測定や亀裂の深さ評価に優れており、厚い部材や複雑形状でも適用可能です。また、放射線を使用しないため、安全性の面でも有利です。ただし、接触面の準備や検査員の技量によって精度が左右されることがあります。検査対象によっては、表面研磨やカップリング材(ジェル)の使用が必要です。
その他の非破壊検査手法
ろう付け後の非破壊検査には、X線や超音波以外にもいくつかの手法があります。
液浸浸透探傷検査(PT)
液体の浸透液を接合部に塗布し、毛細管現象で微細な表面欠陥に浸透させます。その後、現像剤で液体を浮かび上がらせ、欠陥を可視化します。表面の微細な割れやピンホールを検出するのに適しています。
磁粉探傷検査(MT)
磁性体の接合部に磁場をかけ、表面や表面近くの欠陥に磁粉が集まる現象を利用する方法です。表面割れや隠れた亀裂の検出に有効ですが、非磁性材料には使用できません。
渦電流検査(ET)
電磁誘導の原理を用い、導電性材料の表面や近傍の欠陥を検出します。薄板や細かい部品の表面状態を確認する際に有効で、接触せずに検査できるメリットがあります。
適切な検査手法の選定
ろう付け後の非破壊検査では、製品の材質や形状、接合部の重要性に応じて適切な手法を選定することが重要です。
- 航空機部品や高負荷部品: 内部欠陥の早期発見が必須なため、X線や超音波検査が中心
- 自動車部品や量産部品: コストや検査時間を考慮して、超音波や液浸浸透検査を併用
- 複雑形状や薄板: 渦電流検査や液浸浸透検査が有効
複数の手法を組み合わせることで、表面・内部の欠陥を網羅的に確認することができます。特に安全性が重視される部品では、X線で内部を確認した後、液浸浸透や磁粉検査で表面欠陥をチェックする二段階の検査体制が推奨されます。
非破壊検査の今後の展望
近年、非破壊検査技術はデジタル化や自動化が進んでいます。X線検査ではデジタルラジオグラフィ(DR)が普及し、フィルム現像の手間が削減されるだけでなく、画像処理による欠陥判定の精度も向上しています。超音波検査では、フェーズドアレイ技術により、1回のスキャンで広範囲の内部情報を取得できるようになっています。
また、AIや機械学習を用いた画像解析技術により、人手による判定のバラツキを減らし、欠陥検出の精度向上が期待されています。将来的には、生産ライン上でリアルタイムに非破壊検査を行い、品質を自動で保証するシステムも実現可能です。
まとめ
ろう付け後の非破壊検査は、製品の安全性・信頼性を確保する上で欠かせない工程です。X線検査や超音波検査をはじめ、液浸浸透検査、磁粉探傷検査、渦電流検査など多様な手法があります。それぞれの方法には特徴や適用範囲があり、材質や形状、接合部の重要性に応じて選定することが重要です。
また、近年ではデジタル化やAIの活用により、検査精度の向上と効率化が進んでいます。これにより、より安全で高品質なろう付け製品の供給が可能となり、製造現場の品質管理体制の強化にも寄与しています。非破壊検査の理解と適切な活用は、ろう付け技術を用いた製品開発・量産において、今後ますます重要性を増す分野であると言えるでしょう。
いかがでしたでしょうか?
金属加工.comでは、他にも金属加工関連の情報を発信しております。他にも気になる記事がありましたら、是非ご覧ください。
金属加工.comのトップページはこちら↓

関連記事はこちら↓