ろう付けの融点・沸点について
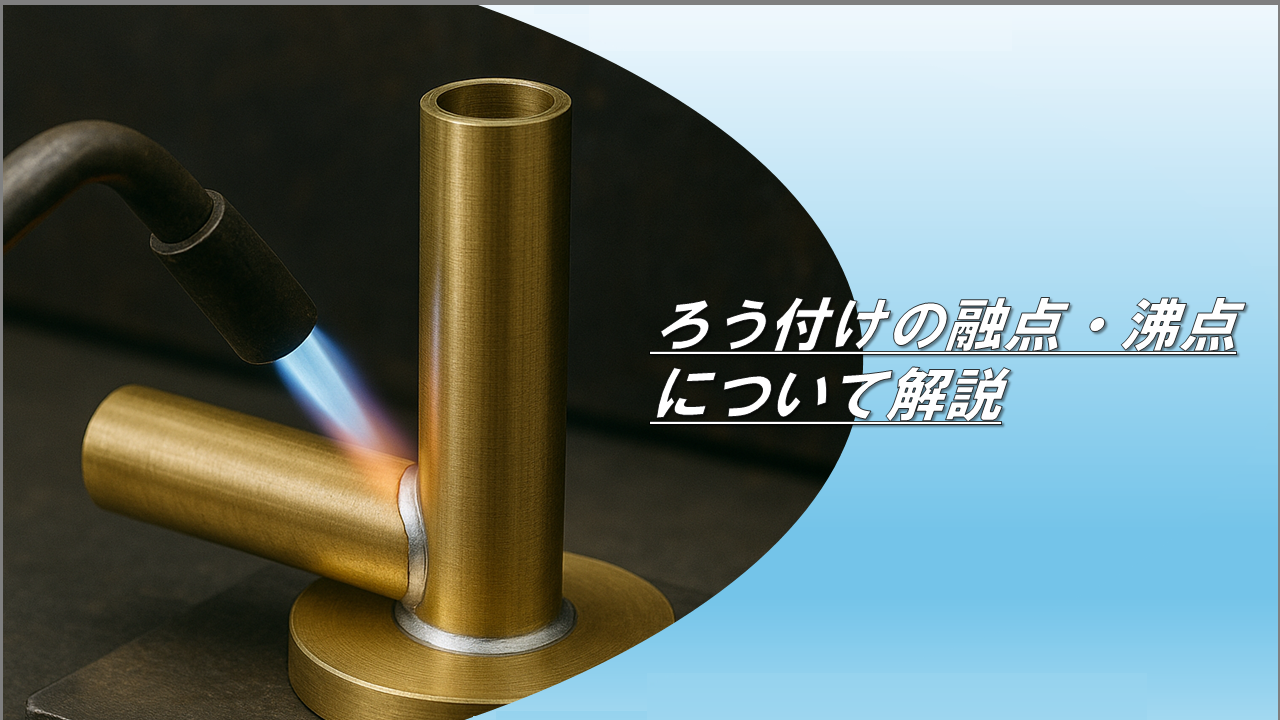
はじめに:ろう付けとは
ろう付け(英語では “brazing”)は、接合方法の一種であり、一般的には母材(ベースメタル)よりも融点が低い金属材料(ろう材)を加熱して溶かし、その溶融金属を毛細管現象や濡れ性を利用して接合部に流し込み、母材同士を接合する技術を指します。ろう付けには、接合温度がおおむね450℃以上のものを指すケースが多く、それよりも融点が低いはんだ付け(ソルダリング)とは区別されます。一方、溶接(ウェルディング)は母材そのものを溶かして接合するため、融点やエネルギーの観点でも大きな違いがあります。
ろう付けの利点は、母材をあまり溶かす必要がなく、母材が持つ機械的特性を大きく損なわない点や、接合部の仕上がりが比較的きれいになりやすい点などが挙げられます。また、適切なろう材を選択することで異種金属同士の接合も比較的容易になります。一方で、母材表面の酸化膜や油分を除去するためにフラックスを使用したり、ろう材によっては高価な合金成分を含む場合もあるため、コスト面での検討が必要な場合もあります。
ろう材の定義と特性
ろう材とは何か
ろう材(英語では“filler metal”または“brazing filler metal”)は、ろう付け時に接合部へ補充される合金や金属材料です。ろう材の種類は実に多岐にわたり、銀・銅・亜鉛・アルミニウム・ニッケル・リンなどのさまざまな元素が合金として組み合わされます。ろう材の選択において重要となる要素は以下の通りです。
- 融点(溶融温度)の範囲
母材より融点が低いことが望ましいが、過度に低すぎると十分な強度を得にくい場合もある。 - ぬれ性(溶融したろう材が母材をどの程度濡らすか)
ろう材が母材表面に十分に広がらないと、強固な接合が得られない。 - 機械的性質
接合部が必要とされる強度・耐久性を満たすか。 - 耐食性・耐熱性
接合体が使用される環境により、ろう材の耐食性・耐熱性などを考慮する必要がある。 - 熱膨張係数などの物理的特性
異種金属を接合する際に、温度変化による伸縮が異なると熱応力が大きくなる場合がある。
ろう付けに使われる代表的なろう材としては、銀ろう(銀-銅-亜鉛系、銀-銅-ニッケル系など)や銅ろう(銅-リン系、銅-亜鉛系など)、アルミニウムろう材(アルミニウム-シリコン系など)、ニッケル系ろう材などがあります。これらは接合対象となる金属の種類や使用環境に合わせて選択されます。
ろう材の融点に関する基礎知識
融点と固相線・液相線
金属や合金には明確な「融点」が存在するとよく言われますが、特に合金の場合は「固相線(Solidus)」と「液相線(Liquidus)」と呼ばれる温度範囲をもって定義されることが多いです。
- 固相線(Solidus): この温度以下では合金は完全に固相(固体)である。
- 液相線(Liquidus): この温度以上では合金は完全に液相(液体)になる。
合金の場合、固相線と液相線の間に「半溶融状態」となる範囲が存在します。いわゆる“パーステンパー領域”とも呼ばれることがありますが、ろう材にもこうした温度域が存在する場合があります。ろう材のカタログや標準規格を見ても、単一の融点ではなく「融点範囲」として示されるケースが多いのはこのためです。
ろう付けを行う際は、液相線以上の温度に到達させることによってろう材が十分に溶融し、毛細管現象や濡れ性を利用して接合部に流れ込みます。逆に、ろう材の融点範囲が高すぎると母材への熱負荷が大きくなり、母材そのものの特性が低下するリスクがあります。一方、融点範囲が低いろう材では母材をあまり加熱せずに接合できるため、母材に熱的ダメージを与えにくい利点がありますが、接合強度が不足する場合もあるため、用途に合わせたバランスが重要です。
ろう材の代表的な融点
以下に、代表的なろう材の融点(または融点範囲)の例を示します。実際には製品ごとに細かい成分調整が行われており、融点は異なる場合があります。
- 銀ろう(BAg系)
例:銀-銅-亜鉛系合金
融点範囲:およそ600〜800℃前後
銀ろうは展延性(延ばしやすさ、曲げやすさ)に優れ、また濡れ性も良好であるため、ステンレス鋼や銅合金、さらにはニッケル基合金など多様な母材に使用されます。 - 銅ろう(BCu系)
例:銅-リン系(Cu-P系、BCuPと呼ばれる)
融点範囲:700℃台〜900℃台
銅-リン系はリンが脱酸材の役割を果たすため、銅や銅合金をフラックスなしで接合できるのが特長です。ただし、鉄やニッケルなどの母材の場合は別途フラックスが必要です。 - アルミニウムろう材(Al-Si系)
融点範囲:570〜600℃程度
アルミニウムは酸化膜が非常に安定で除去しにくく、接合が難しい金属の一つです。Al-Si系ろう材を用い、適切なフラックス(もしくはフラックス代替のフッ化物処理など)を使うことでアルミニウム同士のろう付けが可能となります。 - ニッケル系ろう材
例:BNi系
融点範囲:800〜1150℃程度(含有成分によって大きく変化)
ニッケル基ろう材は耐熱性・耐食性に優れるため、高温下で使用される機器や化学プラントなどで活用されます。ただし融点が高めであるため、真空炉など高温を扱える設備が必要となるケースが多いです。
ろう材の沸点に関する基礎知識
金属の沸点とは
金属や合金も、理論的には十分な高温に達すると液体から気体へ相転移します。これがいわゆる“沸点”です。ただし、ろう付けの実務レベルでは、ろう材の沸点に達するような高温で作業を行うことは極めて稀です。一般的なろう付けの温度帯は数百度(高くても1,000℃程度)であり、金属の沸点は通常2,000℃以上のものが多いため、作業環境においてろう材が沸騰することはほぼありません。
しかし、合金中の特定の元素(例えば亜鉛など)は比較的低い沸点(約907℃)を持つことがあり、ろう付け温度領域でも気化する可能性があります。特に注意が必要なのは、亜鉛やカドミウムなどが含まれるろう材を高温で加熱した場合です。これらの成分が揮発しやすいと、ろう材の組成が変化してしまい、ろう付け時の特性(融点や濡れ性)に影響を与えることがあります。また、揮発した金属のガスは安全衛生上の問題にもつながりやすいので、局所排気装置など適切な換気設備を整えることが重要です。
沸点が実務に及ぼす影響
実務的には、ろう材の沸点そのものを気にする場面は多くありません。一方、ろう材に含まれる揮発性の高い成分が加熱により酸化やガス化を起こし、接合面にピンホールを生じさせたり、ろう材の組成を変化させたりする問題はしばしば生じます。これを避けるために以下の対策がとられます。
- 真空ろう付け
ろう付けを真空炉で行うことで、空気中の酸素や水分、窒素などによる酸化や窒化を抑制し、金属が揮発・酸化しにくい環境を作り出す。 - 不活性ガス雰囲気ろう付け
アルゴンやヘリウムなどの不活性ガスを炉内に充満させ、同様の目的を達成する。 - 適切なフラックスの選定
フラックスは酸化膜を除去し、ろう材の濡れ性を向上させるが、加熱時にろう材やフラックス成分が過度に揮発しないように、適切なタイプを選択する。 - 加熱プロファイルの管理
必要以上に急激な過熱や高温保持を行わず、できるだけ安定した温度上昇を心がける。
また、ろう材メーカーのデータシートには、融点範囲だけでなく成分における沸点や蒸気圧特性に関する注意が記載されている場合があります。特に亜鉛やカドミウムなどが含まれるろう材を扱う場合は、作業者の安全と接合品質の両面から、十分に留意しなければなりません。
融点・沸点と安全性
有害成分の取り扱い
前述のように、ろう材には亜鉛やカドミウムといった比較的沸点の低い成分が含まれている場合があります。これらが加熱によって揮発すると、有害ガスとなって作業環境を汚染する可能性があります。カドミウムは特に毒性が強く、取り扱いには厳重な安全対策が求められます。
現代ではカドミウム含有のろう材は規制が強化され、使用が禁止または制限されている国や業界も多くなりました。安全面だけでなく、環境規制(RoHS指令など)の観点からも、カドミウム含有のろう材は敬遠される傾向にあります。代替としてカドミウムフリーの銀ろう材などが広く普及していますが、コストや接合特性の違いがあるため、現場の要件に応じた選択が重要です。
熱中症・火傷リスク
ろう付けは数百度以上に達する高温を扱うため、作業者は火傷や熱中症などのリスクに晒されます。特にロウ温度が高い溶接・ろう付け作業では、防護具(耐熱手袋、エプロン、保護眼鏡など)の着用が必須です。作業場の換気や温度管理も欠かせません。融点や沸点に関連した安全対策という文脈では、ろう材が揮発・飛散した場合の局所排気装置や、酸素濃度を監視する機器などを設置しておくとより安全です。
ろう材の選定と融点・沸点の実務的考察
用途別のろう材選定
- 空調・冷却装置など銅配管のろう付け
銅-リン系のろう材がよく用いられます。銅同士の接合ではフラックスが不要な場合もあり、比較的低コストで安定した作業が可能です。融点は700〜800℃前後が一般的で、沸点まで到達することはまずありませんが、リンの揮発や酸化には注意が必要です。 - ステンレス鋼のろう付け
銀ろう(Ag-Cu-Zn系)やニッケル系ろう材などが用いられます。ステンレス鋼は不動態皮膜を形成しており、酸化膜が比較的安定しているため、ろう材が濡れにくい場合があります。フラックスや雰囲気炉の使用が一般的です。温度レンジは600〜900℃程度が多く、高温側になると亜鉛の一部が揮発する可能性があります。 - アルミニウム同士のろう付け
アルミニウム-シリコン系のろう材(融点約570〜600℃)を用いるのが一般的です。大気中で作業する場合は塩化物系フラックスなどを使用し、酸化膜を除去します。アルミニウム自体の融点(約660℃)よりも低めの融点を持つろう材を選ぶ必要があるため、合金設計が限られています。沸点に注意が必要な成分(例:亜鉛など)があまり含まれないため、安全面では比較的扱いやすいですが、高温を維持しすぎると母材が溶けてしまうリスクがあります。 - 耐熱性・耐食性を求める高温部品のろう付け
ニッケル系、コバルト系のろう材が使用され、ろう付け温度は800〜1150℃程度に及びます。タービンブレードやジェットエンジン部品、化学プラントの熱交換器など、過酷な環境下に置かれる金属部品の接合に使われます。高温に達するため、亜鉛など低沸点金属の揮発リスクが高まるかと思いきや、ニッケル系ろう材にはそもそも亜鉛などが含まれていない場合が多いので、主な注意点は真空炉や不活性ガス炉を用いた酸化・汚染防止策となります。
コストと作業性のバランス
融点が低めのろう材は作業温度が低くて済み、母材の歪みや熱影響を抑制できますが、一般的に高価な銀や特別な合金成分を多く含む場合もあります。一方、融点が高めであればコストを抑えられることがありますが、加熱装置やプロセス制御が複雑になり、母材が受ける熱影響も大きくなるため、歩留まり(不良率)の増加やエネルギーコストの増大などのデメリットもあります。
実際には、単純に融点だけでなく、「目標とする接合強度」「使用温度範囲」「工作精度」「量産性」「安全規制への対応」など、多角的な観点でろう材が選定されます。また、特に大規模な生産ラインでは、自動化装置やろう付けロボットとの適合性、作業者の技量や工程時間の制約なども考慮しなければなりません。
ろう材の融点・沸点に関するトラブルシューティング
ろう付けプロセスでありがちなトラブルと、その原因・対処法をいくつか挙げてみます。
- ろう材がうまく流れない
- 原因: 母材表面の酸化膜や汚れ、フラックス不足、加熱不足など。
- 対処: 母材を十分に前処理し、適切なフラックスを使用する。また、炉やトーチの出力を見直し、液相線を十分に超える温度を確保する。
- 接合部にピンホールやボイドが生じる
- 原因: ろう材やフラックスに含まれる成分のガス化、急激な加熱、母材やフラックス中の水分など。
- 対処: 真空炉や不活性ガス炉を利用し、加熱プロファイルを緩やかに設定。必要に応じてフラックスの種類を変える。
- 接合強度が期待値より低い
- 原因: 過剰加熱や不足加熱によるろう材組成の変化、母材の脆化、フラックスの劣化など。
- 対処: 適正な温度管理、母材の前処理状態のチェック、使用後のフラックスやろう材の保管方法の見直しなどを行う。
- ろう付け中に有害ガスが発生する
- 原因: 亜鉛やカドミウムなど低沸点金属が揮発、フラックスが高温で分解して有毒ガスを放出など。
- 対処: 揮発性の低いろう材への切り替え、排気装置・換気設備の強化、防護マスク着用など安全対策を徹底する。
- 母材が溶けてしまう(溶融・溶食)
- 原因: 使用したろう材やフラックスが母材を侵食しやすい成分を含む、あるいは過剰な高温により母材自身の融点を超えてしまった。
- 対処: 母材と相性の良いろう材・フラックスを選ぶ。温度プロファイルを再検討し、必要以上に長時間高温を維持しない。
まとめ
ろう付けに用いられるろう材の融点と沸点は、接合プロセスの設計や安全管理において非常に重要な要素です。特に実務レベルでは「融点」よりも「融点範囲(固相線・液相線)」が重視され、ろう材がどの温度で確実に液相となり接合を行えるかが焦点になります。一方、金属の沸点は非常に高温域に存在することが多いため、ろう付け温度で金属そのものが沸騰するケースは稀ですが、揮発性のある元素を含む場合は組成変化や安全上のリスクを伴うことがあります。
ろう材は多様な合金設計がなされており、典型的には銀-銅-亜鉛系、銅-リン系、ニッケル系、アルミニウム-シリコン系などが一般的に利用されています。これらは母材との相性や使用温度、接合強度、耐食性などによって選択されます。また、近年は環境規制や安全規制の観点から、カドミウム含有のろう材の使用が制限される傾向にあり、代替としてカドミウムフリーのろう材が普及している状況です。
実際のろう付け作業では、母材の加熱方法(トーチ、炉、誘導加熱など)、フラックスの選定、雰囲気制御(真空炉、不活性ガス炉など)が大きく品質に影響します。融点・沸点そのものだけでなく、加熱速度や保持温度、冷却速度などの加熱プロファイルがろう材の特性や最終的な接合部の強度・外観・信頼性を左右します。特に亜鉛など低沸点成分を含むろう材を高温域で使用する際は、組成変化やガス発生に注意し、十分な排気や保護具を備える必要があります。
総合的に見れば、ろう材の融点・沸点を理解することは、ろう付けプロセスを最適化する上で必須の知識です。母材との組み合わせや使用環境、コスト、量産性、安全規制への対応など、さまざまな要件を総合的に考慮し、最適なろう材と作業条件を選択することが高品質で安定したろう付けには欠かせません。
